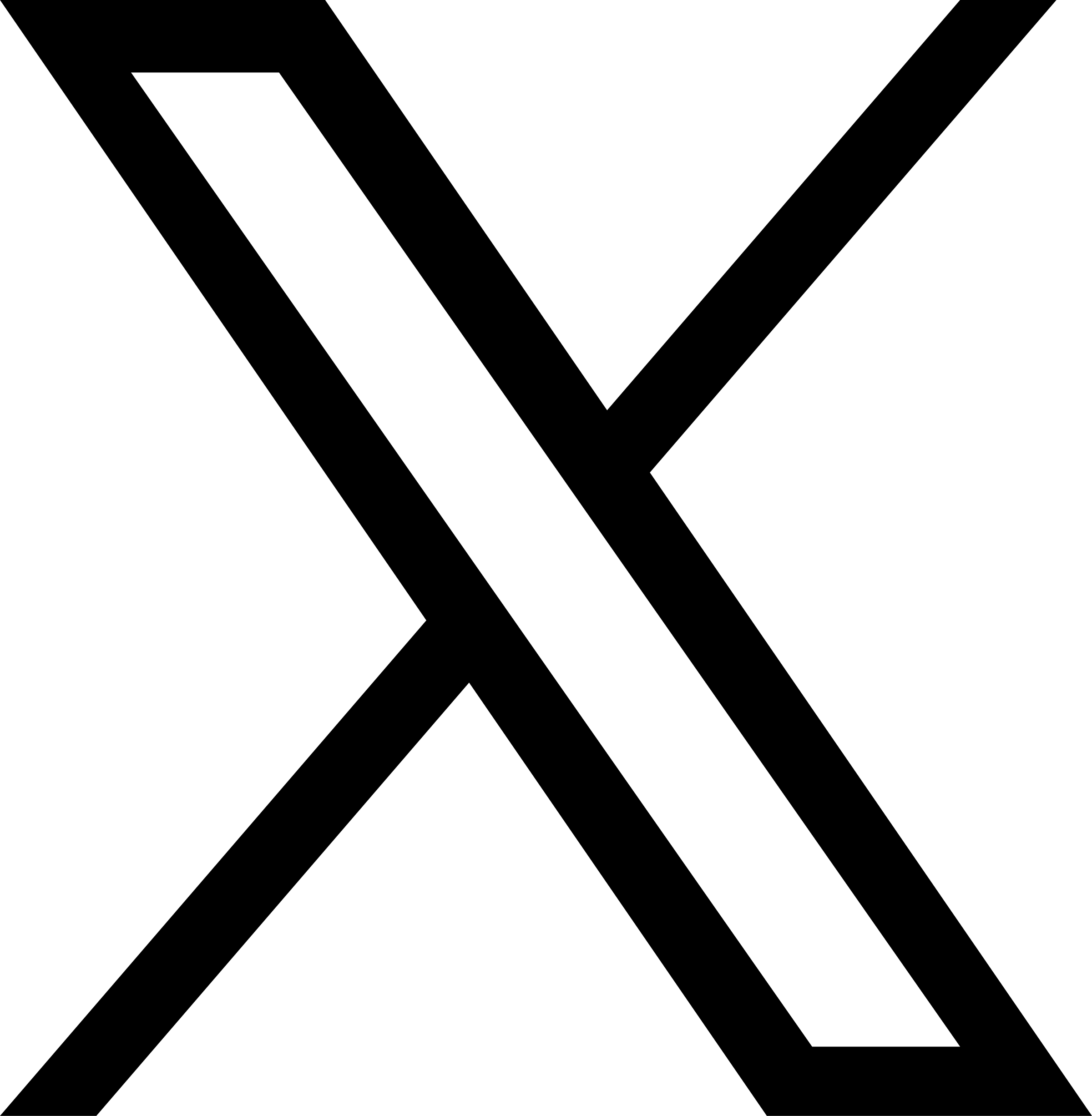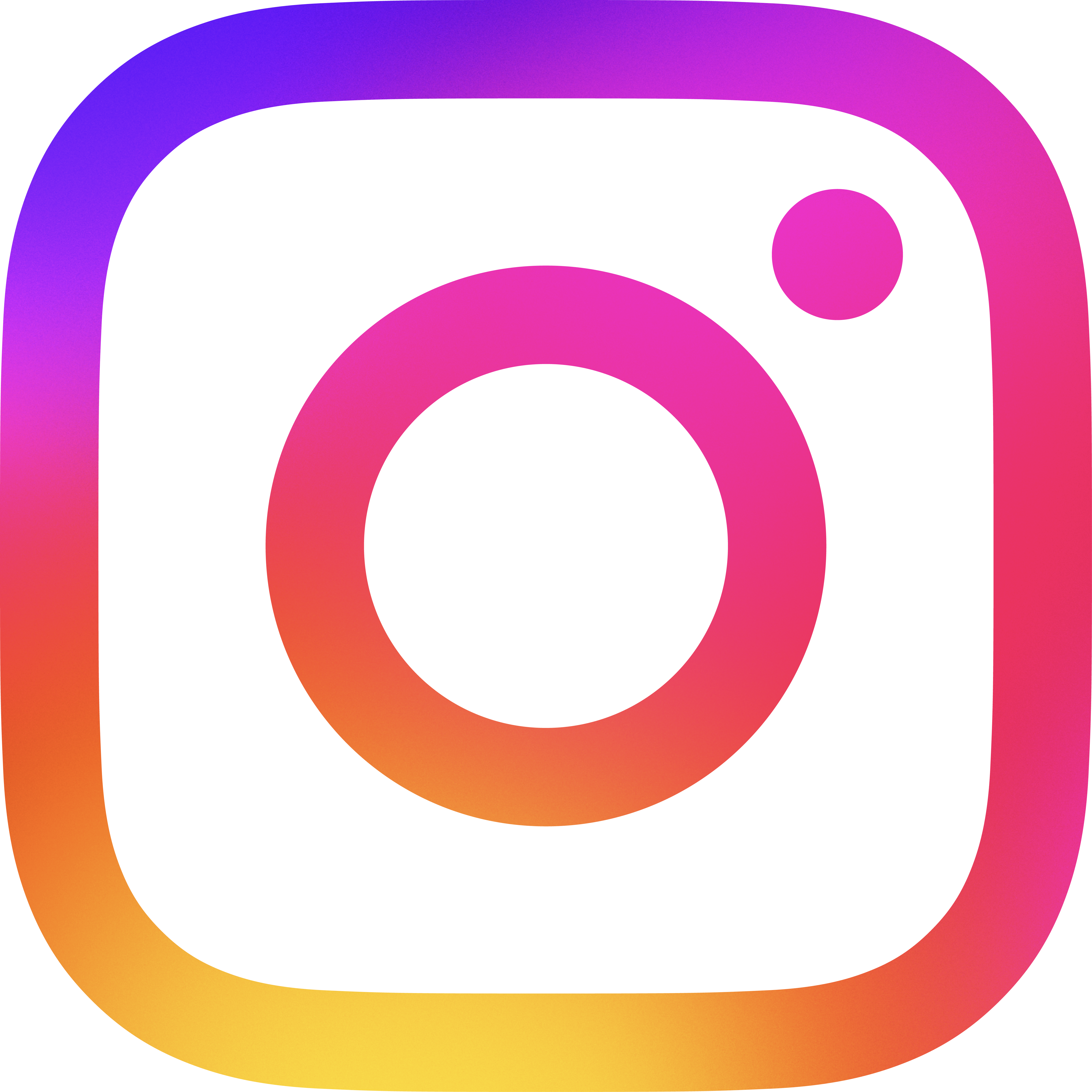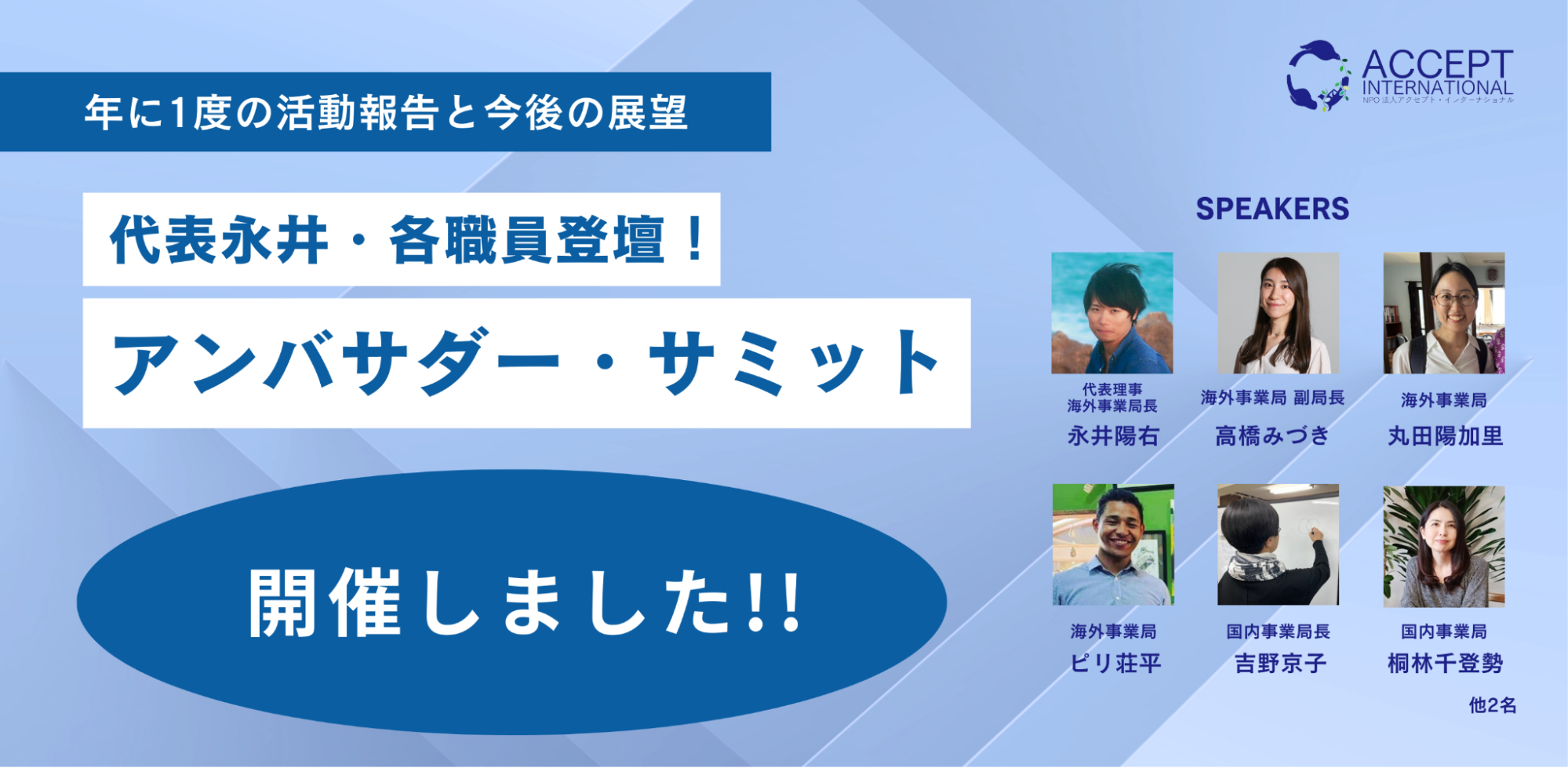 アンバサダーの皆様に昨年度の活動報告と今年度の展望についてお伝えする「アンバサダーサミット」を、今年度も開催いたしました。
アンバサダーの皆様に昨年度の活動報告と今年度の展望についてお伝えする「アンバサダーサミット」を、今年度も開催いたしました。
当日は約3時間にわたり計8名の職員より詳細に活動を共有させていただきました。昨年までとは一線を画し、各事業部から担当者が直接報告を行うことで、より多角的な視点から私たちの活動についてお伝えすることができました。
※アンバサダーの方で見逃してしまった方やイベント後にアンバサダーにご就任いただいた方は、support@accept-int.org までご連絡ください。本イベントのアーカイブ動画をお送りいたします。
本記事ではイベントの内容について簡単にご紹介します。
1. 2024年度総括
まず、全体的な収支報告を代表・永井からご説明させていただきました。2024年度は、アンバサダーの年間純増数が601名と過去最高になりました。
またアンバサダーの増加に伴い、全体の収入が前年度と比べると4,200万円ほど増加し、総額約3.5億円規模となりました。収入の内訳は、委託・助成金が約60%、寄付金は全体の38%を占めており、その中でも特にアンバサダーの皆様からの毎月のご寄付の総額は約4,500万円に上ります。その他単発寄付や法人からのご寄付と合わせて約1億700万円のご寄付をいただきました。
私たちの独立した紛争地での活動は、皆さまのご寄付により支えられています。委託や助成金は用途が限定されるため、ソマリア、イエメン、パレスチナなどにおける紛争当事者への、非常に重要であるものの難しい、前例のない活動は、まさに皆さまのご寄付があってこそ実現できるものです。
改めて2024年度も温かなご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
2. 各事業部活動報告
今回から、各事業部の実施事項だけでなく、どのような壁に直面しそれらをどう乗り越えたのかについてもお話しさせていただきました。
① ソマリア事業部
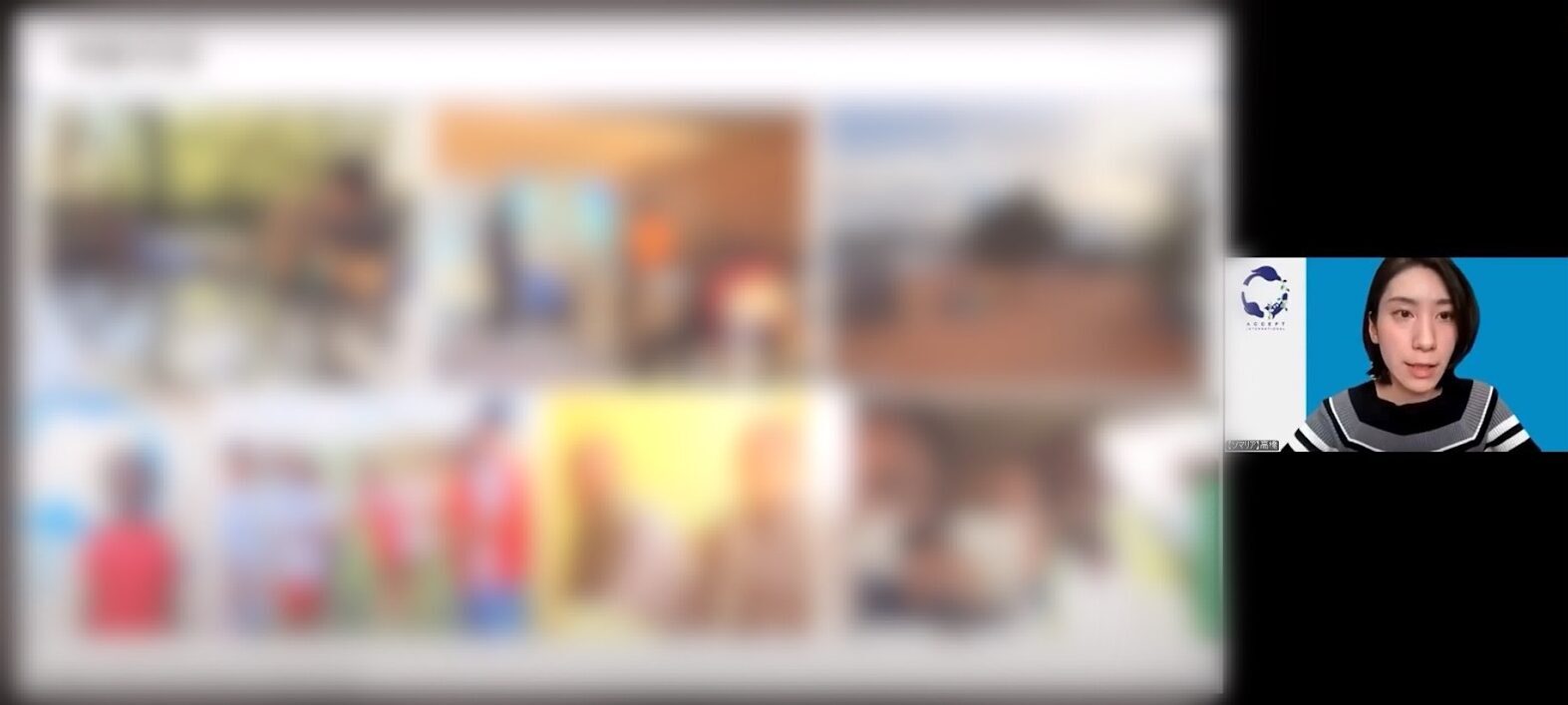
▲ 登壇者:海外事業局副局長 高橋みづき
ソマリアでは1980年代に勃発した内戦が今も続いており、アフリカ大陸で最も危険なテロ組織とされるアル・シャバーブが広く支配地域を持っています。私たちはそのような紛争の最前線で、活動を続けています。
2024年度はアンバサダーの皆さまから栄養豊富なモリンガを用いたレシピを募集し、リハビリ施設における食事改善も行いました。モリンガに加えてユーカリなども豊富に自生しているため、今後もアンバサダーの皆様と一緒に栄養豊富なメニューを増やしていければと考えております。
一方で、投降促進のためのリーフレット配布においては、アル・シャバーブの指揮官がリーフレットを全て燃やしてしまい戦闘員たちに情報が行き渡らないという問題も発生してしまいました。
この壁を乗り越えるため、戦況の変化に応じてリアルタイムに展開しているソマリア国軍やアフリカ連合軍にリーフレット配布を依頼し、前線地域のコミュニティの方たちとの信頼関係を築いて協力を得る体制を構築しました。
② イエメン事業部

▲ 登壇者:イエメン事業担当 丸田陽加里
2015年から続く紛争により、異なる目的を持つ様々な勢力が乱立するイエメンにおいて、反政府武装組織フーシ派が支配する北部地域と政府の支配地域の境界に近い前線で活動しています。
2024年度は初の試みとして、捕虜収容所内にメッセージボードを設置し、苦しい状況にいる若者たちが前向きな気持ちになれるよう、アンバサダーの皆様からの応援メッセージを募集しました。リハビリ施設に来た時だけでも前向きな気持ちになれるような環境構築に取り組んでいます。
③ ケニア事業部

▲ 登壇者:ケニア事業部担当 ピリ・カ二ャーキーソ荘平
東アフリカの経済的中心の一つであるケニアにおいて、アル・シャバーブによる攻撃や若者が暴力に巻き込まれるケースが後を絶たない中、過激化防止のための包括的支援や刑務所における受刑者のリハビリテーションを実施しています。
2024年度はナイロビの刑務所で脱獄事件が起き、ケニア全体でセキュリティが一気に強化され、私たちのプログラムの実施も危ぶまれました。
しかし、関係者に対して活動の目的や有効性を丁寧に説明し、面談などを通して少人数グループや柔軟なスケジュールへ切り替えるなど工夫を重ねることで、活動の継続を現地政府・社会に受け入れてもらうことができました。
今後は既存の刑務所での支援継続に加えて、出所者が地域社会との繋がりを取り戻すため、地域住民を招いた対話セッションを予定しています。
④ インドネシア事業部
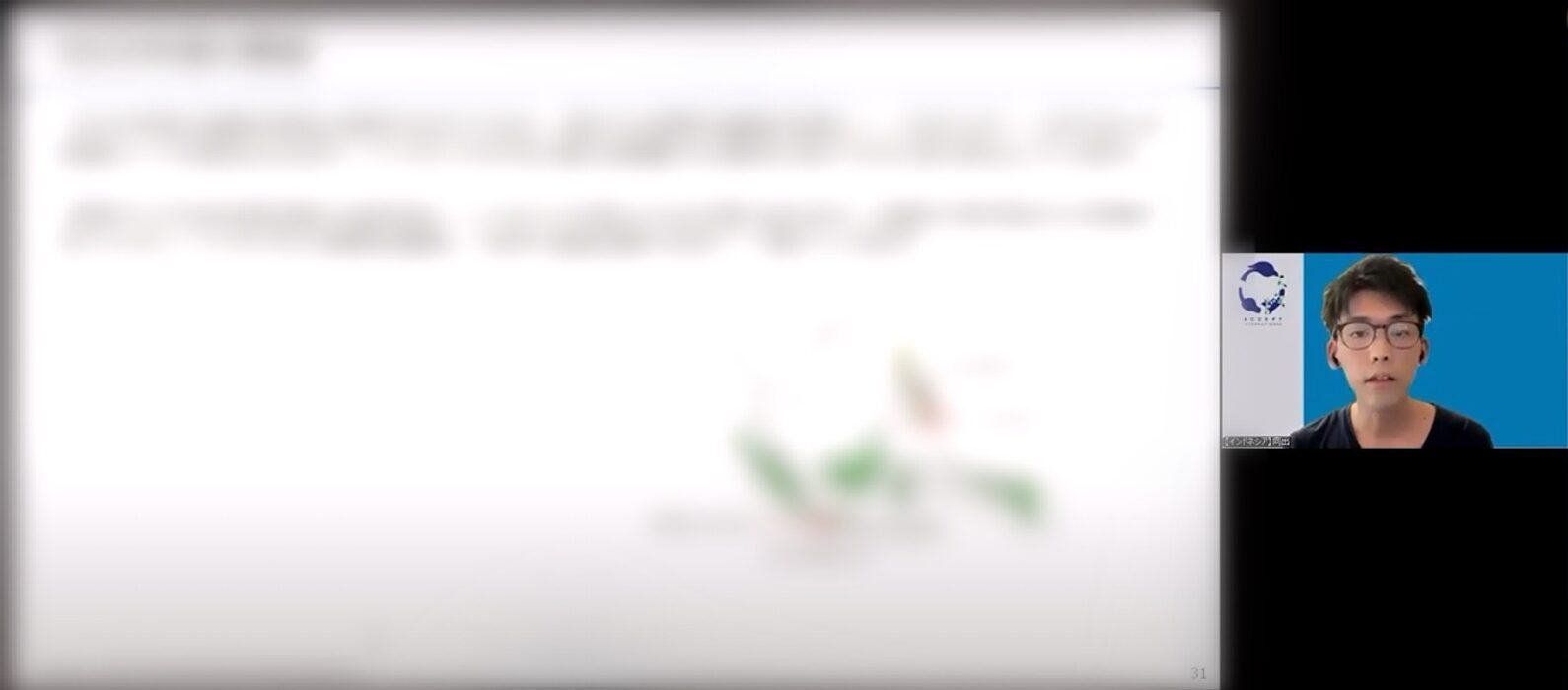
▲ 登壇者:インドネシア事業部長 向出洋祐
あまりテロのイメージがないインドネシアですが、テロ容疑で刑務所に収監されている受刑者に対する適切なリハビリや社会復帰支援がなく、過激な思想を抱いたまま出所したり、社会に馴染めずに再びテロに関与してしまう例が報告されています。
2024年度は、インドネシアの監獄島として知られる特にリスクの高い受刑者が集められた中部ジャワ州のヌサカンバンガンを起点に、テロリスト受刑者を対象としたリハビリと社会復帰支援を実施しました。
私たちのインドネシアにおける活動は、NHKワールドのAsia Insightsという番組でも紹介していただきました。
今後は得られた知識や経験を生かしながら、東南アジアを含む周辺国にも目を向け、支援から取り残された若者が多いフィリピン・ミンダナオなどにも事業を展開し、世界に蔓延する憎しみの連鎖をまた一つほどいていきます。
⑤ コロンビア事業部
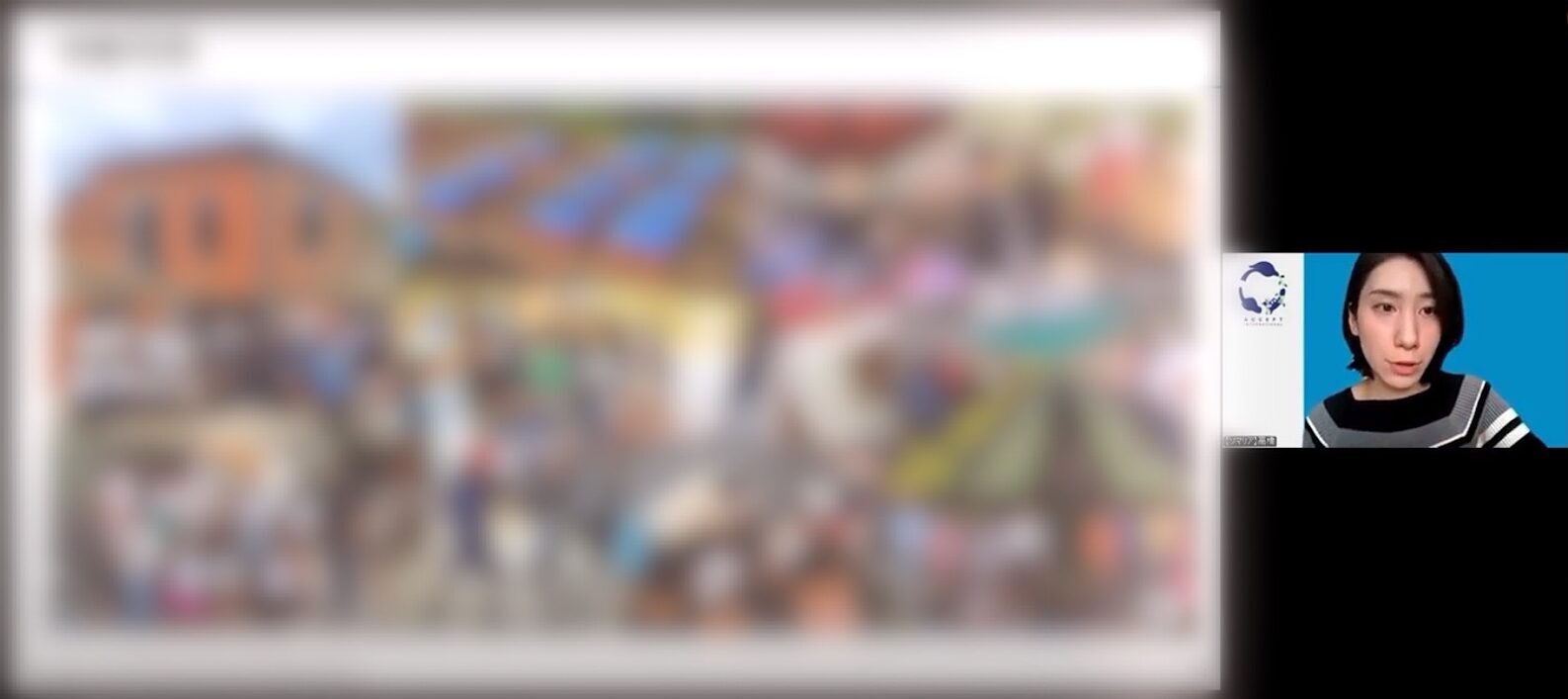
▲ 登壇者:コロンビア事業部長 鈴木真代
時差のため代理報告:海外事業局副局長 高橋みづき
コロンビアは50年以上にわたって、主にコロンビア革命軍という共産主義系の武装勢力との紛争が続いてきました。和平合意はあったものの、未だ元戦闘員が社会に戻っていくのが難しい状況を踏まえ、主に地域との和解に重点を置き活動を行っています。
例えば地域コミュニティの公道に看板を設置し、多目的職業訓練センターの存在を知らせ、地域の方々と元戦闘員の交流の機会を増やしたり、元テロ受刑者の子供たちのカウンセリングを行ったりと、様々な観点から持続的な平和の実現を目指しています。
⑥ パレスチナ事業部
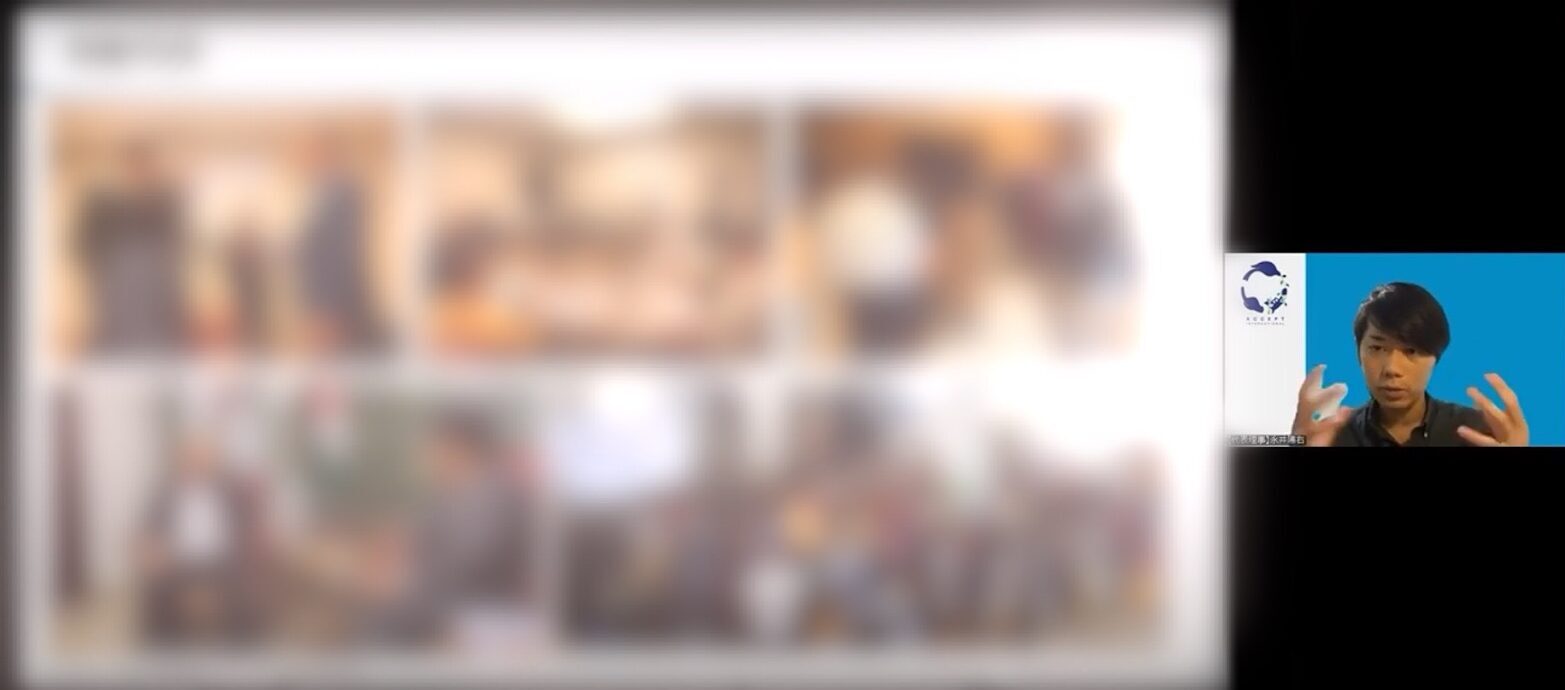
▲ 登壇者:代表理事 永井陽右
約80年近く続くパレスチナ・イスラエル間の衝突において、2023年10月7日からさらに情勢が混迷を極める中、世界的にガザ地区における人道支援は行われているものの、新たな和平のプロセスを見出していくような取り組みが極めて少ない状況にあります。
活動開始当初はパレスチナの人々から「なぜ俺たちが変わる必要があるんだ、人殺しをしているのはイスラエルじゃないか」といった意見もあがりましたが、これまでの経験で培った経験などを交えながら対話を重ねることで、徐々に新たな和平につながる対話プロセスの構築に対して賛同してもらうことができました。
今後は国際的なネットワークと現地の若手リーダーたちをさらにつなげ、欧米諸国や他のアジア諸国なども巻き込んでさらなる対話の枠組みを広げていきます。
⑦ 国際規範制定
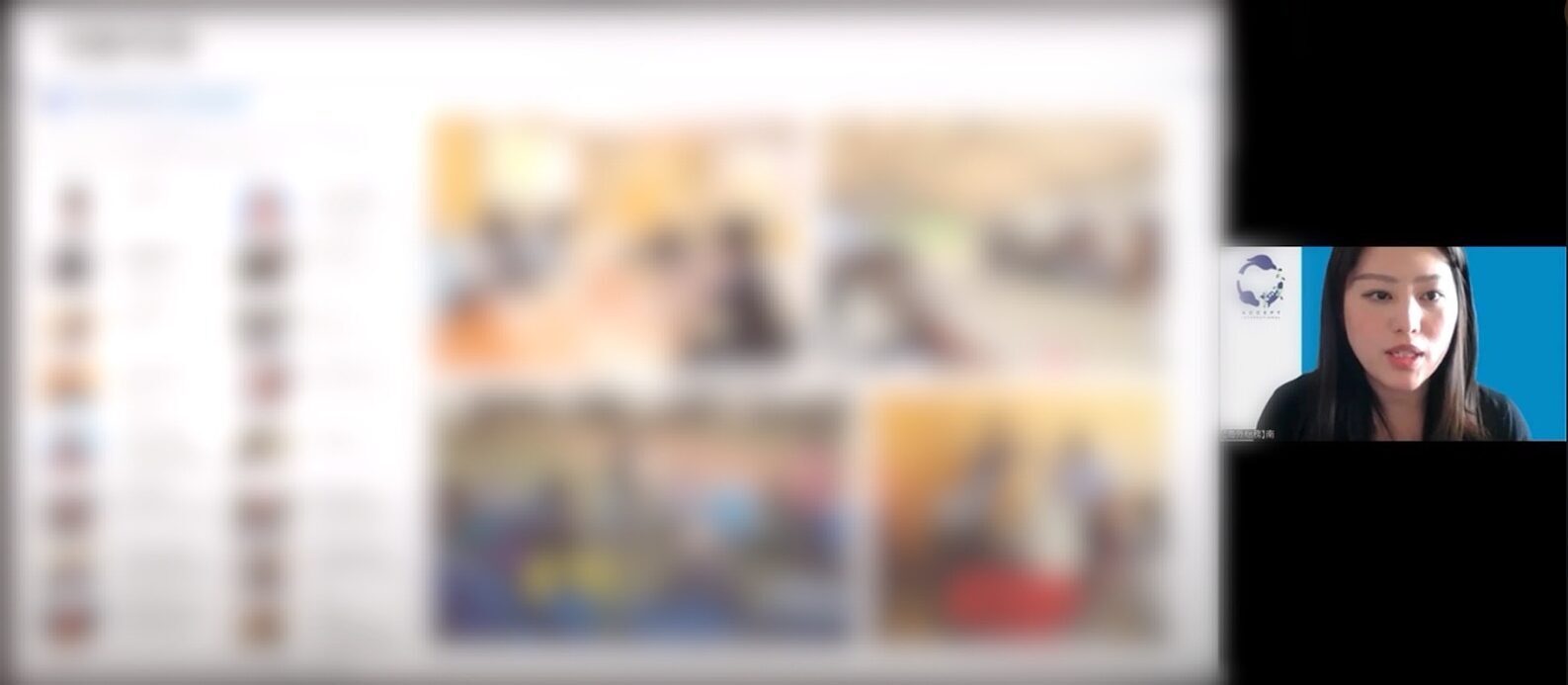
▲ 登壇者:国際規範制定チーム 南優菜
紛争地などの最前線での取り組みに加えて、国際政策という最上流の領域において、元戦闘員の若者の社会復帰を支える新たな国際規範の制定に向け活動しています。
18歳以下の子ども兵は国際法で保護されている一方で、私たちが支援しているような18歳を超えた年齢の若者の元戦闘員は、現在の国際的な枠組みでは取り残されている現状があります。
2024年度はさまざまな地域からこの取り組みへの賛同者を集め、テロや紛争に関わっていた若者や専門家などによるタスクフォース「Global Taskforce for Youth Combatans(GTY)」の設立を実現しました。また、世界15ヵ国において元戦闘員の若者に対するニーズ調査を行い、彼ら彼女らと共に200ページもの教科書を作成するなど、彼ら彼女らに特化したプログラムの作成を行いました。
現在はオックスフォード大学やニューヨーク大学などさまざまな専門機関とも連携・話し合いを進めています。引き続き複数の国の政府と関係構築を進めつつ、来年2月に予定されている国連人権理事会決議の採択を目指してまいります。
⑧ 在日外国人支援事業部
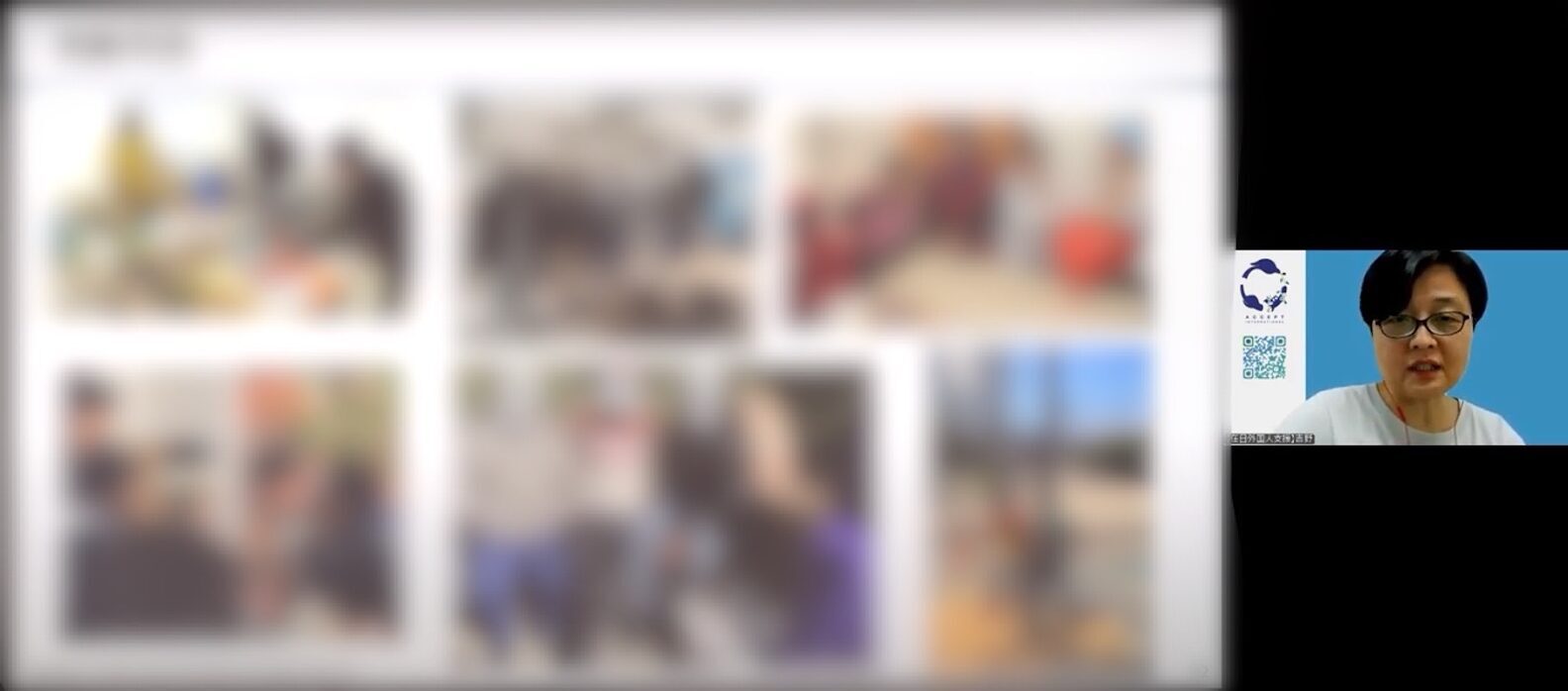
▲ 登壇者:国内事業局長 吉野京子
難民認定申請中で在留資格が不安定な方、日本の公的支援を得ることが困難な方を対象に、緊急宿泊支援、食料・医療・衛生支援、日本語学習指導、在留資格等のサポートを実施しました。
支援の受け皿が非常に少ない方々に対し、公的な支援を得られるまでのつなぎ支援として大いに貢献することができました。
⑨ 更生支援事業部
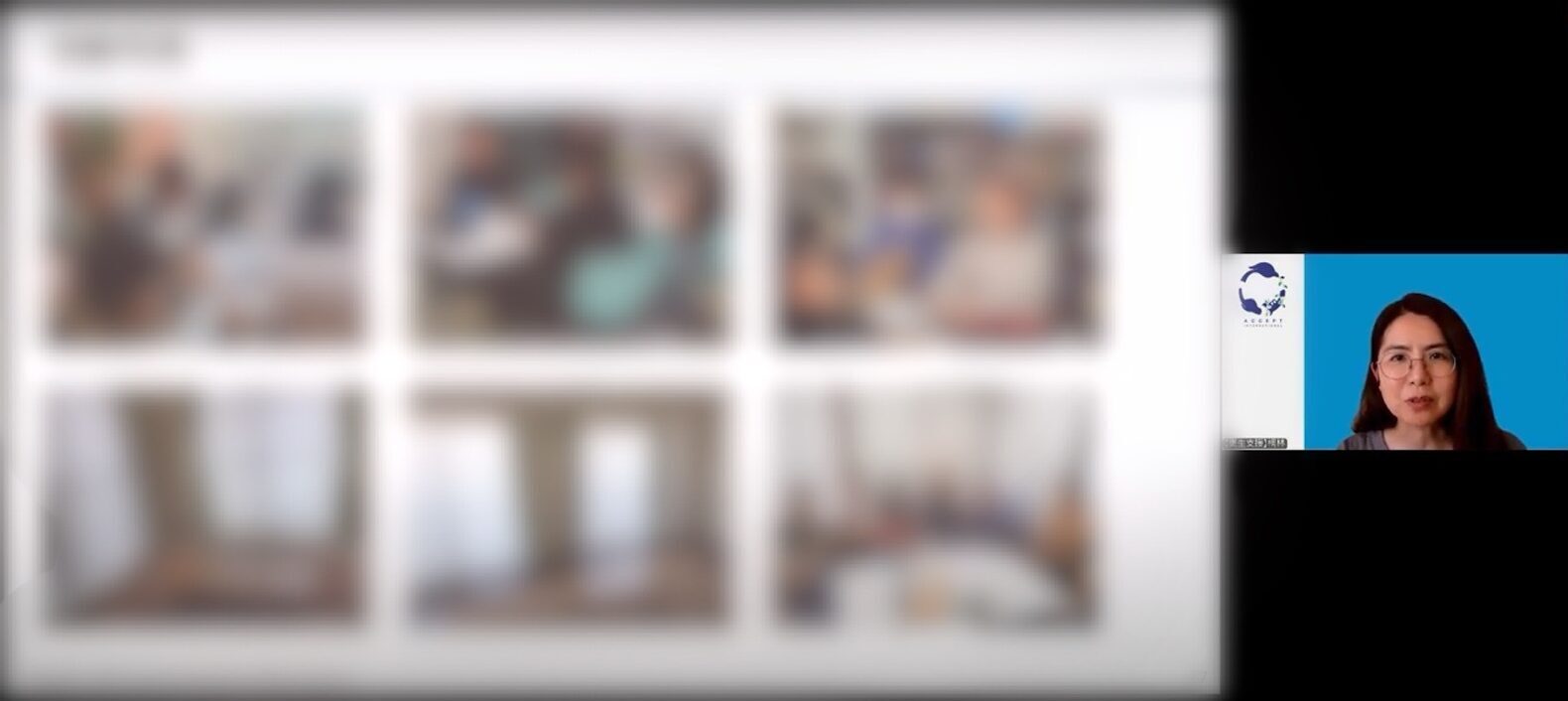
▲ 登壇者:更生支援事業部長 桐林千登勢
少年院や刑務所などの矯正施設を出た若者や、親や身近な大人に頼ることのできない若者に対し伴走支援を実施しています。相談対応や住居の提供に加え、調理や金銭管理のトレーニングといった生活支援、さらに歌舞伎町での声かけ活動など、包括的な支援を展開しました。
また、法務省東京矯正管区への交渉の末、8月1日より川越少年刑務所で刑務所ラジオを実施することが決定しました。「自分自身とつながり、社会とつながり、様々な支援とつながり、未来につながるための情報を届ける」をコンセプトに、代表・永井をパーソナリティに含めた収録音声を放送します。他の矯正施設や一般への展開、英語での刑務所ラジオも検討中です。
3. 質疑応答セクション
各事業部からの報告後、海外事業・国内事業それぞれに関して参加者の皆様から多岐にわたるご質問をいただきました。
以下にいくつかの質問をご紹介します。各回答はぜひアーカイブ動画をご覧ください!
「各国のキーパーソン、重要な方々との交渉や対話の場が多いかと存じます。緊張感がある場で、どのような話や行動が相手の心に響くのでしょうか」
「支援されている方々がなぜ日本を選んで来られるのか、その経緯について教えてください」
「団体としてのリソースが限られる中で多岐にわたる事業を行う上での難しさやそれを乗り越えるために意識しているポイントを教えてください」
4. 懇親会の様子

イベント終了後には東京都内で懇親会を開催し、アンバサダーの皆様と職員が交流を深めました。奈良や三重、京都や愛知など遠方から駆けつけてくださった方もおり、大変貴重な時間となりました。
イベント終了後に実施したアンケートでも、参加者の皆様から多くの温かな感想をいただきました。
「それぞれの事業部の方が直接発表されるのが大変良かったです。2024年度振り返りも、みなさま個人個人で感じられた多様なご経験が伺え、活動理解が深まり親近感も強くなりました!」
「各国での報告を聞き、ジワジワと成果が出ていることに、心動かされるものがありました。『対話』の取り組みが広がっているのをみて、自分も励まされました」
「質疑応答が充実していたのが嬉しかったです。引き続き強みを活かしながら課題に取り組み成果を出し、活動範囲も広げているのがわかって、支援のモチベーションも上がりました」
「皆さん笑顔でお話ししておりましたが、想像以上に困難な問題に向き合い活動されている、という事がわかりました。私自身も生きる上で励みになりました。誠にありがとうございます」
5. 最後に(今後の展開:代表理事・永井)
イベントの最後には、代表理事・永井より今後の展望をお伝えしました。その一部抜粋を持って、本記事を締めさせていただきます。
「2025年度は、2020年に立てた5カ年計画が終了する年です。現在その時掲げた目標値と大きな乖離なく、目標を順調に達成することができています。続く5年では、5億円から10億円規模の組織に成長することを目標としています」。
「今後より多くの方々が参加できるよう、東京、そして佐賀におけるふるさと納税など、さまざま手札を広げていきつつ、収入規模とともに仕事の規模・質量を増やしていきたいと計画しております」。
「私たちのパーパス(存在意義)は誰しもが平和の担い手となり共に憎しみの連鎖を解いていくです。先進国の大都市の優秀な人たちだけではなく、例えば武装勢力にいる・いた若者など、様々なバックグラウンドを抱えた人であっても、誰しもが平和の担い手になることができます。むしろ彼らこそユニークな平和の担い手になれる可能性に溢れています」。
「引き続き日本から紛争解決と平和構築の地平を開いていきます。私たちがこのパーパスを実現し尽くすまで、引き続き温かなご支援をいただけますと幸いです」。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。ぜひこの機会に皆様もアンバサダーとして支援の輪に加わっていただければ幸いです。
※現在アンバサダーではない方に関しましても、アンバサダーご登録後support@accept-int.org までご連絡いただければ、本イベントのアーカイブ動画をご視聴いただけます。お気軽にお問い合わせください。