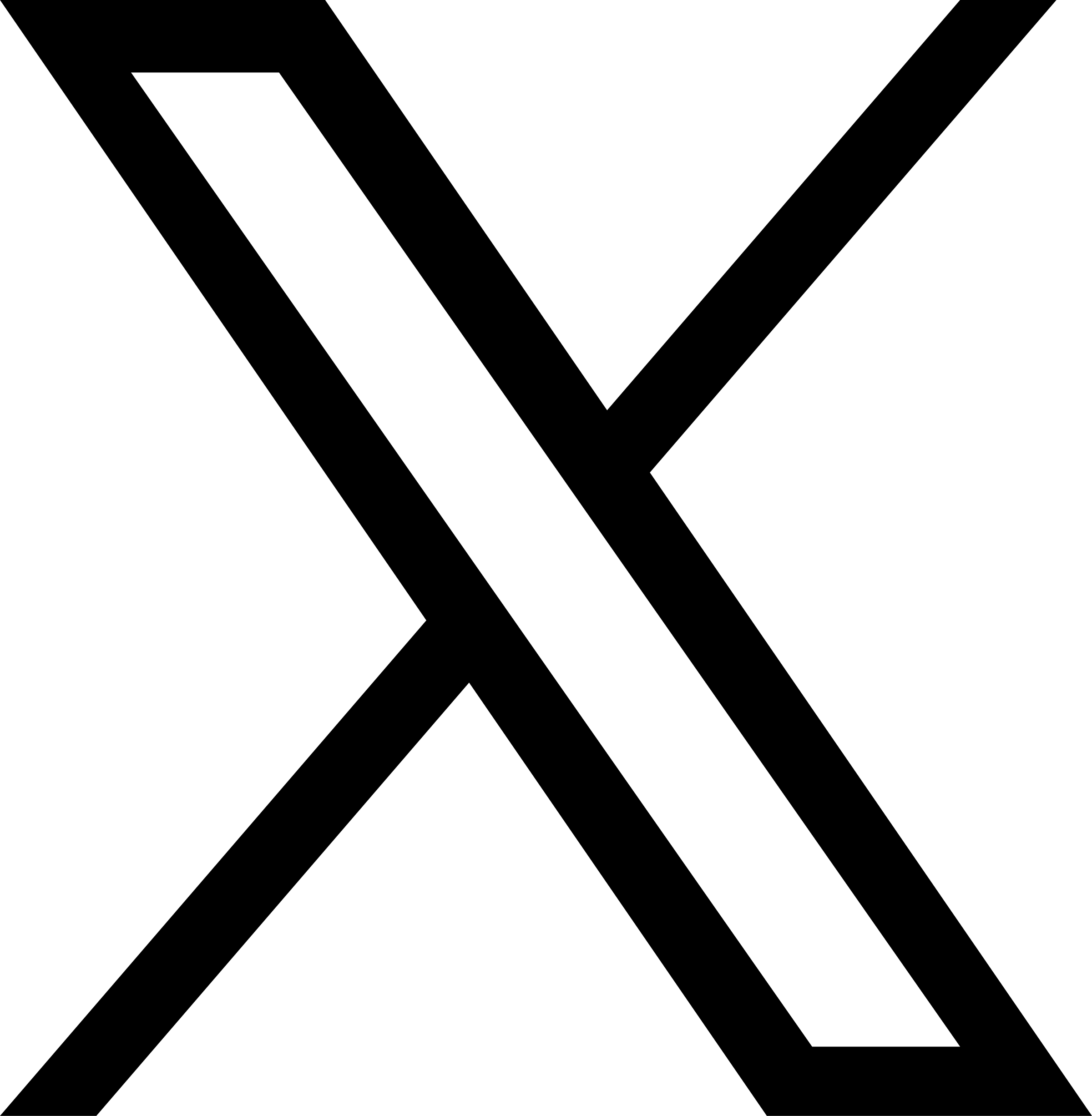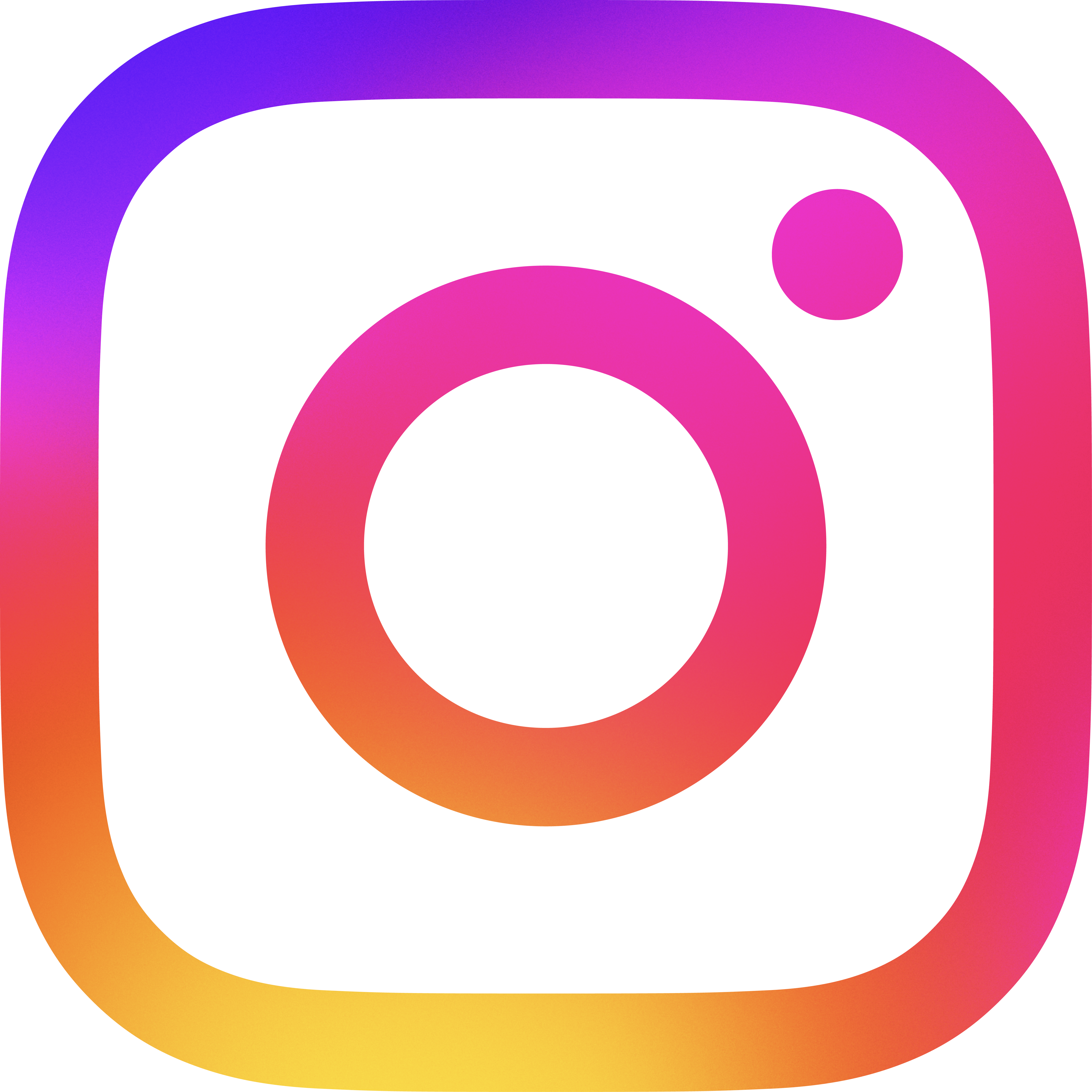[2025年9月]

今回は国際規範制定に向けた取り組みの進捗についてお届けします。
1.国際規範制定の取り組みとその背景について
近年、国際社会では若者が「未来をつくるリーダー」として注目されています。SDGsや平和構築を目指す取り組みの中でも、若い世代や彼ら彼女らが担う役割が重要視されています。
一方、私たちは、テロや紛争が続く国や地域で活動を続ける中で、いわゆるテロ組織の中にも、数多くの若者たちが関わっている現実を見てきました。また、そうした若者たちの多くは過激な思想に共感したという理由以上に、誘拐や強制的な参加、貧困や社会的な排除、そして政府や国際社会への怒りといった理由から、やむを得ずテロや紛争などの暴力に関わってしまったという現実も目の当たりにしてきました。
しかし、そのようなテロや武力紛争に関わる若者(Youth Associated with Non-State Armed Groups: YANSAG)も未来の社会を担う大切な存在です。彼ら・彼女らは、過酷な経験を経た上で「平和に貢献したい」という強い意志と、実際に社会を変えていくユニークな平和の担い手となる可能性を秘めています。しかしながら、これまでは単に脅威として見なされ、国際社会において究極的に取り残されてきました。
また、18歳未満のいわゆる「子ども兵」は基本的に「紛争の被害者」と見なされ、国際的に保護の対象になります。この背景には「子ども兵」を守るためのさまざまな国際規範の存在があります。一方で、武装組織に所属している18歳以上の「若者」を守るような国際規範は存在しておらず、「紛争の加害者」として一面的に扱われる傾向にあります。
そこで私たちは、設立10周年を迎えた2021年に「テロや武力紛争に関わる若者の権利宣言」を発表しました。この宣言を皮切りに、世界中でテロや紛争に関わった若者一人ひとりが再び社会の中で自分の力を発揮し、平和の担い手として歩んで行くための指針となる国際規範の制定に向けた取り組みを進めています。
具体的な取り組みとしては、大きく次の3つです。
①国際規範制定に向けたアドボカシー活動の実施
テロや武力紛争に関わる若者の権利やエンパワーメントに関する国際的な認識を高めるため、国際会議やシンポジウムの開催・参加、世界各地の当事者の証言収集などを実施しています。

▲国連経済社会理事会への参加
②エンパワーメントプログラムの開発・実施
各国の教育機関や専門機関と連携し、私たちがこれまで紛争地を中心に培ってきた知見や、世界15カ国以上での証言収集を踏まえ、世界中の紛争当事者が平和の担い手となるための包括的なプログラムを開発・実施しています。
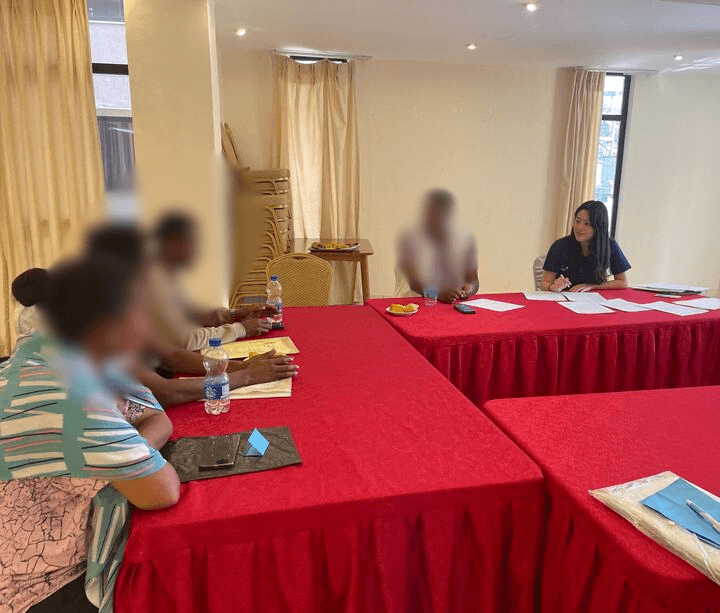
▲世界各地のYANSAGの証言収集の様子。写真はエチオピア。
③グローバルタスクフォースの設立・運営
国際規範の制定に向けて紛争の当事者や被害者などを巻き込み、彼ら・彼女らが取り組みの主体となっていくための若者戦闘員グローバルタスクフォース(Global Taskforce for Youth Combatants: GTY)を設立・運営しています。
今月の活動報告では、このGTYの進捗を中心にお伝えします。
2.GTYとしての取り組み
GTYでは、世界各国から集まったテロや紛争の当事者、関連分野の専門家や実務者、そしてテロや紛争の被害を受けた人々などと共に、オンラインイベントや国際会議の開催などを通じたグローバルな啓発活動を進めています。
さらに、世界各地で紛争当事者であった若者の声から証言を集めるほか、提言文書・規範の条文作成といった取り組みも行っています。
また、テロや武力紛争に関わる若者がユニークな平和の担い手となるためのエンパワーメントプログラムの開発・実施に加え、彼ら・彼女ら自身による活動や、それを支える人々の取り組みを支援する助成事業なども展開しています。
2024年度の助成事業では、2024年12月中旬から2025年1月末にかけて世界中から募集を行った結果、世界各地から200件以上の応募があり、紛争解決や持続的な平和の実現に貢献する草の根プロジェクトを中心に選考を進めました。
その結果、2024年度は次の2つのプロジェクトを助成することとなりました。
①【ナイジェリア】武装組織ボコ・ハラムにいたYANSAGの支援プロジェクト
ボコ・ハラムやその他の過激派組織の活動により10年以上紛争下にあるナイジェリア北東部にて、テロや武力紛争に関わる若者(Youth Associated with Non-State Armed Groups: YANSAG)へ包括的な支援を展開するプロジェクトです。
ナイジェリア北東部では貧困や教育機会の不足など、社会的に脆弱な立場にある若者が武装組織へ加入してしまう状況が続いていました。さらに、仮に若者が武器を置いて地域コミュニティに復帰したとしても、コミュニティ側に彼らを受け入れる土壌がなく、彼らが孤立・失業してしまい、再度憎しみの連鎖に巻き込まれてしまう状況にありました。
そうした中、本プロジェクトリーダーのアダム氏は、現地のYANSAGに対して「ストーリーテリング」のトレーニングを行っています。ストーリーテリングとは、伝えたい情報や想いを物語として表現し伝えるコミュニケーション技術です。この取り組みを通じて、彼ら・彼女らが自分自身の経験を効果的に語り、地域コミュニティとの和解につなげていくことを目指しています。

▲プロジェクトリーダーのアダム氏
現在もプロジェクトが進行している中、アダム氏よりコメントが届いているためご紹介します。
「私はナイジェリア北東部で育ち、若者が貧困や教育不足に苦しみながら戦闘員として強制的に参加させられる状況を目の当たりにしてきました。このプロジェクトに取り組んだのは、地域の平和構築に貢献したいという強い思いからです。私は常に、取り残された人々の声を社会に届けることに重点を置いてきました」。
「現在は、武装組織に関わった経験のある若者たちと共に、平和の意味を改めて見つめ直し、対話を重ねながら彼らの社会復帰を支援しています。彼らが自らの過酷な過去や背景を語り、地域社会と向き合うことで、少しずつ和解と再出発への道を歩めるよう、真摯に取り組んでいます」。
「こうした若者たちとの対話を通して、平和とは、誰かが与えるものではなく、対話の中に、勇気の中に、そして決して諦めない心の中にこそ芽生えるものなのだと改めて実感しています」。

▲アダム氏(青いキャップを被っている青年)が若者にトレーニングをする様子
②【コンゴ民主共和国】武装組織ワザレンドのYANSAGの支援プロジェクト
近年、武装組織の存在によって激しい暴力の連鎖が続くコンゴ民主共和国の東部にて、武装組織ワザレンドのYANSAGを支援するプロジェクトです。
この地域の若者は貧困に苦しみ、就業先もないことから武装組織に加入してしまっています。また、いくつかの武装組織や地域コミュニティが存在する中、コミュニティ間は相互不信の状態にあり、まともに対話ができていません。それゆえ、仮に若者が武器を置き、社会に復帰したとしても、コミュニティに受け入れてもらいにくい状況が続いています。
こうした中、本プロジェクトリーダーのシルヴァン氏は、コミュニティ間の対話促進や収入創出支援を通じて、若者の社会復帰を後押ししています。

▲プロジェクトリーダーのシルヴァン氏
シルヴァン氏からのコメントをご紹介します。
「私が育ってきたコミュニティは武力紛争、人口流出、若者が活躍する機会の不足といった課題に直面していました。私はこうした環境を変えていきたいのです。若者たちは、自分たちの活動が認められ、評価され、支援されれば、平和構築の担い手になれると確信しています」。
「現在は、仕事がないことを理由に武装組織に加わってしまった若者たちとコミュニティの人々が、相互理解を深めるための対話プロジェクトを行っています。また、こうした若者たちが自立できるよう、小規模から始められる農業の職業訓練も提供しています。若者たちが集まり、互いの経験や痛みを語り合う姿を見ながら、癒しとは、他者の物語に耳を傾けることから始まるのだと確信しています」。

▲コンゴ民主共和国でのプロジェクト
なお、シルヴァン氏が話せるのはフランス語のみのため、助成事業の選考に係る面接時には通訳が必要でした。ここで通訳を務めてくれたのは、同じコンゴ民主共和国から日本に難民として逃れてきていた若者でした。実はこの若者は、私たちが日本国内において支援している難民認定申請者であり、同国の武装組織に騙されて加入させられた過去があります。そのため、自国が置かれた状況に対する理解は深く、ただの通訳に留まらない役割を果たしてくれました。
普段は全く別の活動を展開する海外事業局と国内事業局ですが、このようなシナジーが生まれるのはアクセプトらしさの一つです。

▲助成事業の選考に係る面接の様子。
シルヴァン氏はオンライン会議で参加しています。
3.今後の展望および担当メンバー2名よりコメント
<南 優菜>
「国際規範の制定」や「アドボカシー」と聞くと、かつての自分自身も含めて、多くの方が掴みどころのない印象を持たれるかと思います。私たちが取り組んでいることは、アクセプトが徹底した現場主義を通して紛争地の最前線で蓄積してきた一人一人の若者の物語を大きな声にする試みです。
こうした声の集積が規範となり、また武装組織に関わってしまった若者たちが新たにそうした環境から離脱することを後押しし、社会にポジティブな影響を与える若者へと成長することに繋がっていきます。
直近では、そうした若者の権利などに関して、国連人権理事会における決議の採択を目指しており、スイスへの渡航も予定しています。今後も各事業部の職員や世界中の若者たちと連携しながら、紛争地での取り組みと並行して、国際政策の上流においても真に根本的な紛争解決に繋がる成果を積み重ねてまいります。

<松下 真菜>
国際規範制定に向けた取り組みは、長年にわたり紛争の最前線で若者一人ひとりの声に耳を傾け、真正面から向き合い続けてきたアクセプトだからこそ実現し得るものです。アクセプトがこの課題に取り組むこと自体が、確固たる説得力と深い意義を持ち、平和構築という分野において新たな地平を切り開いているのだと強く感じています。
国連人権理事会決議をはじめとした国際的な合意形成を進め、それを実際の紛争現場へと反映させていく道のりは、決して簡単なものではありません。それでも、テロや武力紛争に関わった若者たちがその過去によって定義され、希望ある未来を諦めてしまうことが決してないよう、現場と国際社会をつなぐ使命を果たしながら、今後もそうした若者たちと共にこの挑戦を粘り強く続けてまいります。

【読者の皆様へ】
私たちは、月1,500円から活動にご参加いただける「アクセプト・アンバサダー」を募集中です。
世界中の暴力に絡め取られた若者を社会一体となって救い出し、新たな道を歩むことを力強く支え、テロや紛争の解決に繋げるために、この機会にアンバサダーとしてご参加いただけたら幸いです。