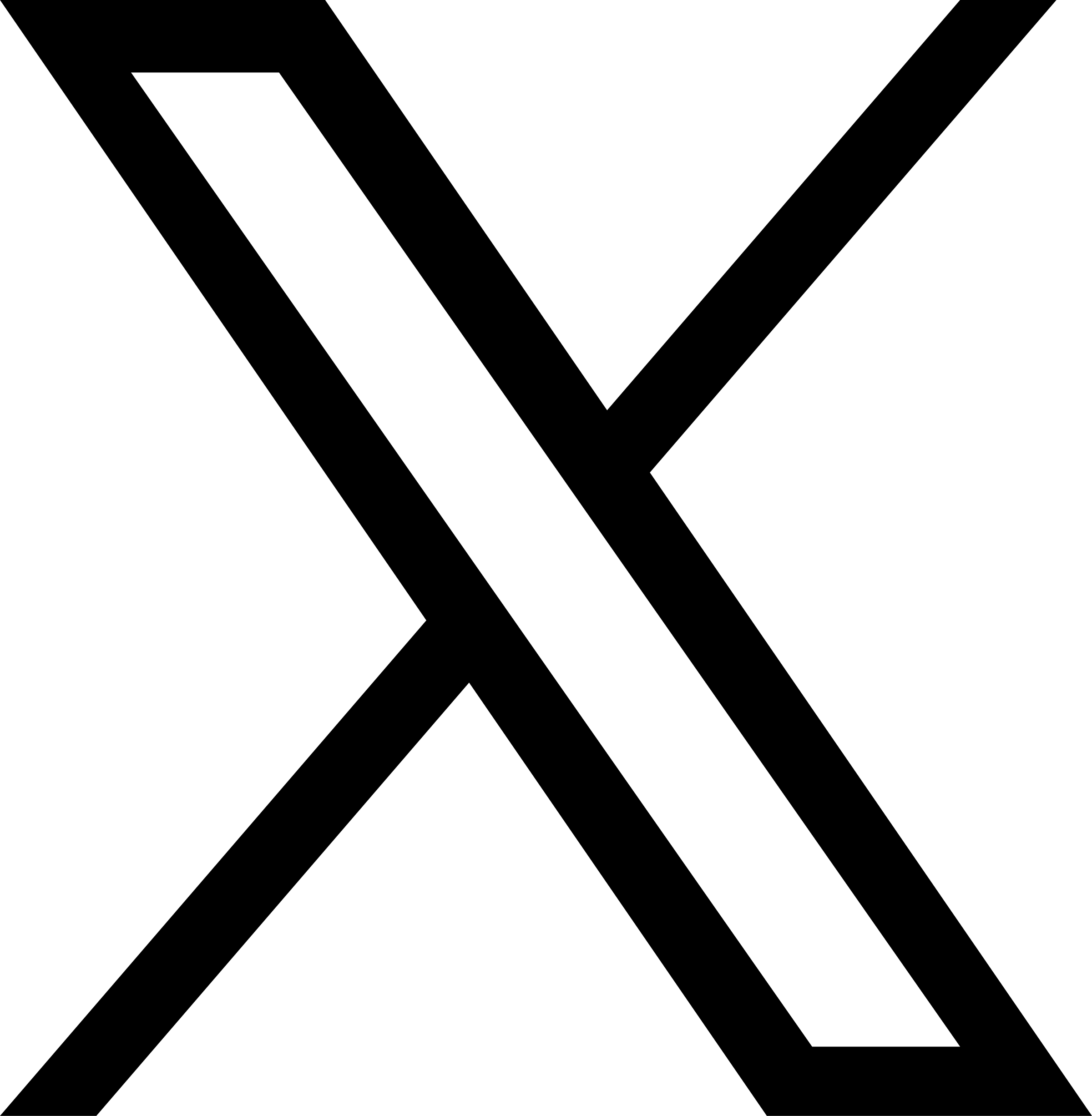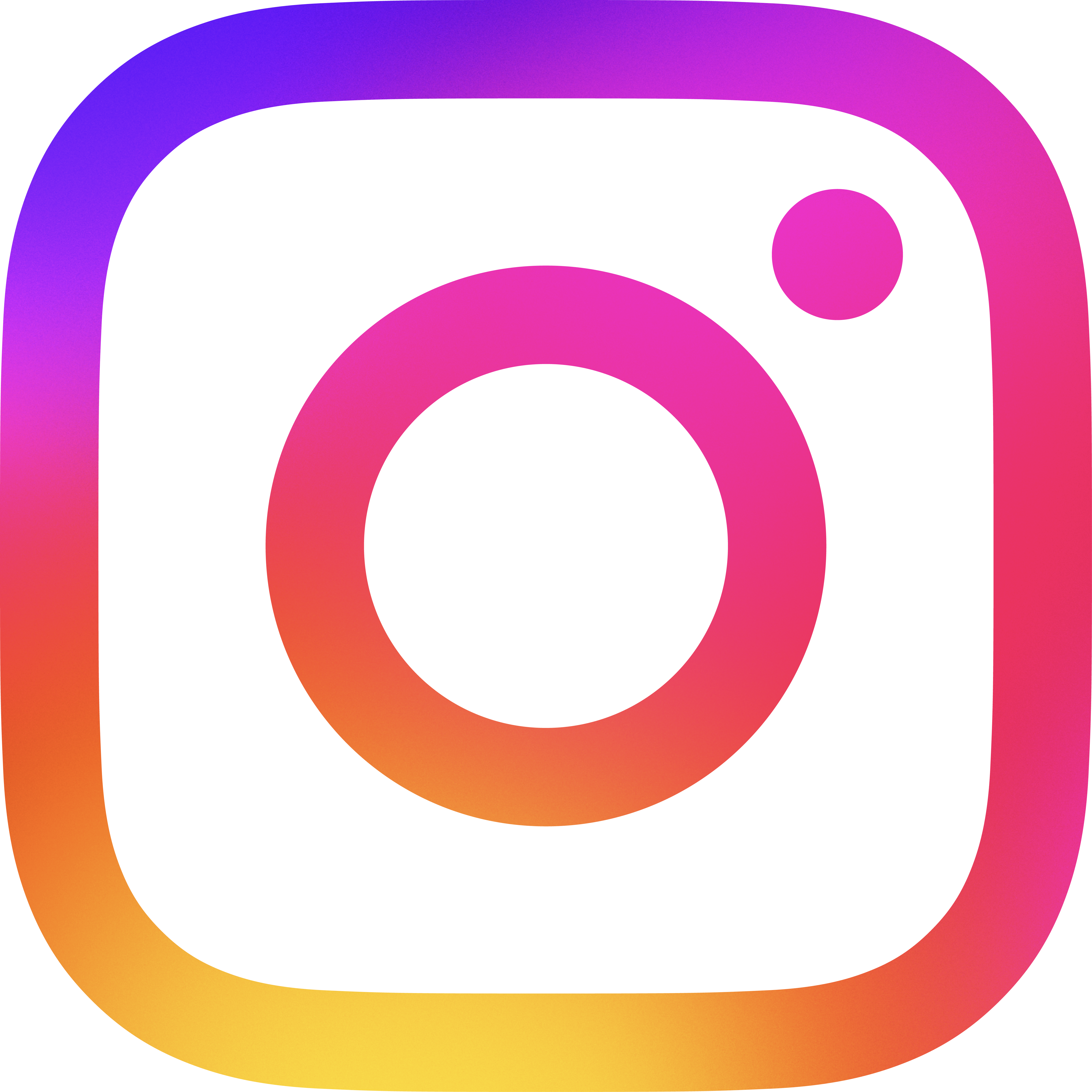私が早稲田大学に入学した2011年、「比類なき人類の悲劇」と形容されていたソマリアを知りました。飢饉や内戦で多くの命が失われているにもかかわらず、当時ソマリアを支援している日本のNGOはほとんどなく、治安の悪化によって国際機関も撤退を余儀なくされる状況でした。
自分に何かできることはないかとさまざまな人に話を聞きにいきましたが、返ってくる答えは、「危険すぎるからやめろ」「安全な場所で経験を積みなさい」「死んでしまったら逆に迷惑だ」というものでした。
しかし、経験やスキルを持った方々が、危険、金にならない、共感できないなどを理由に行動していないじゃないかと憤りました。当時から「大人」や「常識」とされるものに対して強い反発心を持っていたため、そう考えたのです。
そしてだからこそ、大切なのはまずもって問題に対する姿勢なのだと悟り、文字通りのゼロから団体を立ち上げました。当時は仲間と共に出し合った3万円が原資でした。
模索を続けながらも、現地の治安悪化の主要因として恐れられていたソマリア人ギャングへの取り組みを開始しました。同じ若者として彼らを受け止め・受け入れ、対話を通じて再出発を支える取り組みを通じて、彼ら自身が気づき変わっていきました。最終的には、地域三大ギャング組織の解散という確かな成果に繋げることができました。
そうした中、2017年には改めて私・私たちは何をすべきかを考えました。そこで至った結論は、テロや武力紛争といった大きな憎しみの連鎖をほどいていく新たなアプローチを生み出す必要がある、というものでした。考え抜いた末に軸に据えたのは、ギャングたちとの取り組みで学んだ「アクセプト(受け止める・受け入れる)」という姿勢です。
それ以来アクセプト・インターナショナルとして、ソマリアに限らずニーズが非常に高いものの支援の担い手が限られている領域において、独自の活動を展開しています。
また、近年は最前線での活動に加えて、紛争解決のために必要な新しい国際規範の制定に向けて、ジュネーブやニューヨークなどの最上流の現場でも動いています。
以上のような私たちの取り組みは前例がなく、教科書もありません。しかし、前例がないのであれば創る覚悟です。
皆様と共に、ここ日本から、新たなアプローチを生み出し現実化して参ります。どうか温かなご支援を何卒よろしくお願いいたします。

永井 陽右
<プロフィール>
NPO法人アクセプト・インターナショナル代表理事。主にソマリアやイエメン、パレスチナなどの紛争地にて、いわゆるテロ組織を含む非政府武装勢力との交渉や和平に向けた対話構築、非政府武装勢力からの離脱とその後の社会復帰支援、緊急人道支援などを実施。また近年は、テロや武力紛争に関わる若者に関する国際規範の制定に向けても取り組んでいる。国連ではアドバイザリーボード、専門家会議や専門作業部会のメンバー等。オックスフォード大学客員フェロー。京都大学大学院非常勤講師。著書に『紛争地で「働く」私の生き方』(小学館)など。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)紛争研究修士課程修了、早稲田大学社会科学研究科博士後期課程修了。
当法人の取り組みは、継続的なご寄付で活動をご支援いただけるアクセプト・アンバサダーによって支えられています。詳細はこちらのリンクをご確認ください。
-
NPO法人アクセプト・インターナショナル
- 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 YOUビル 6A
- 03-4500-8161 info@accept-int.org