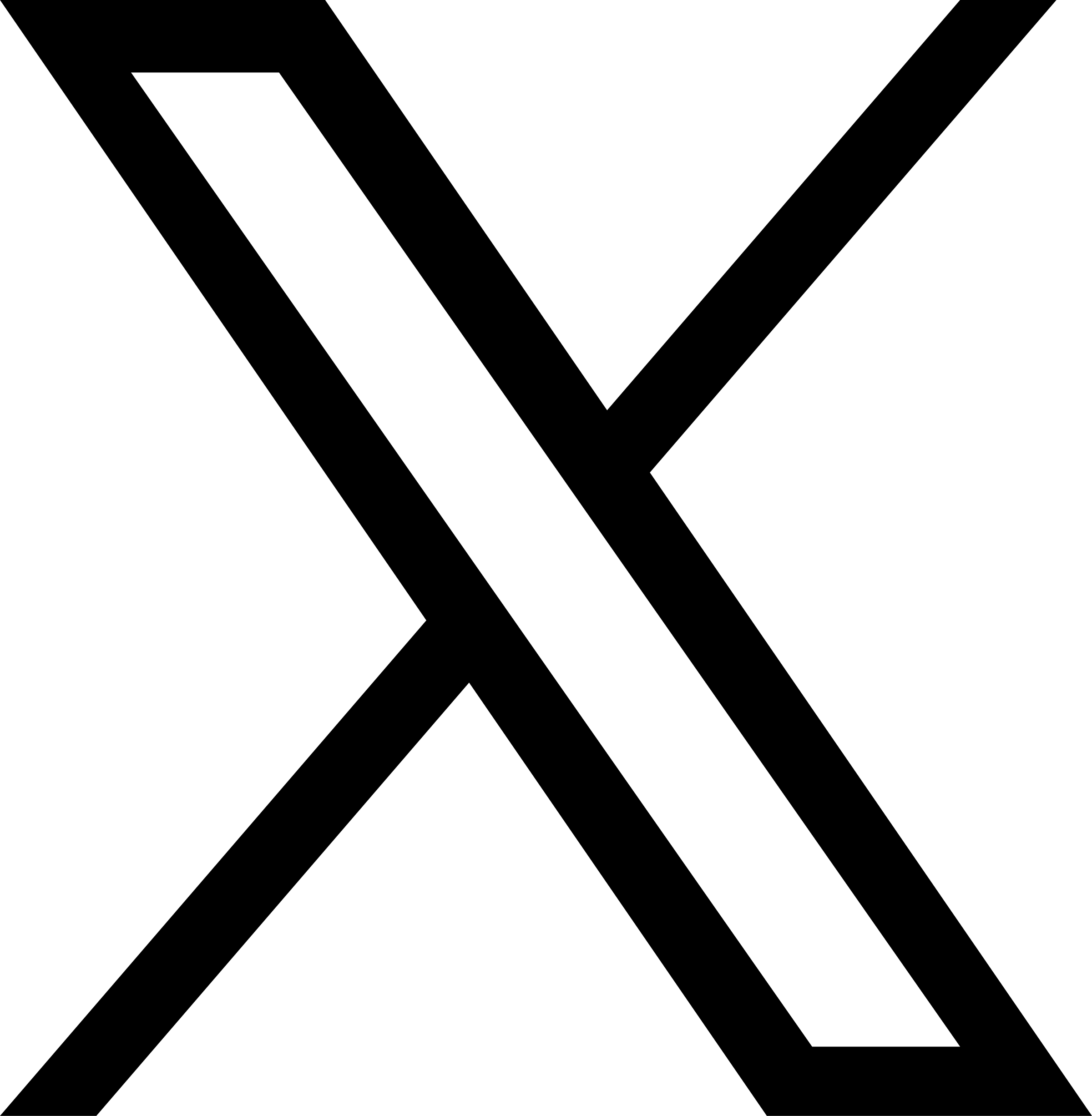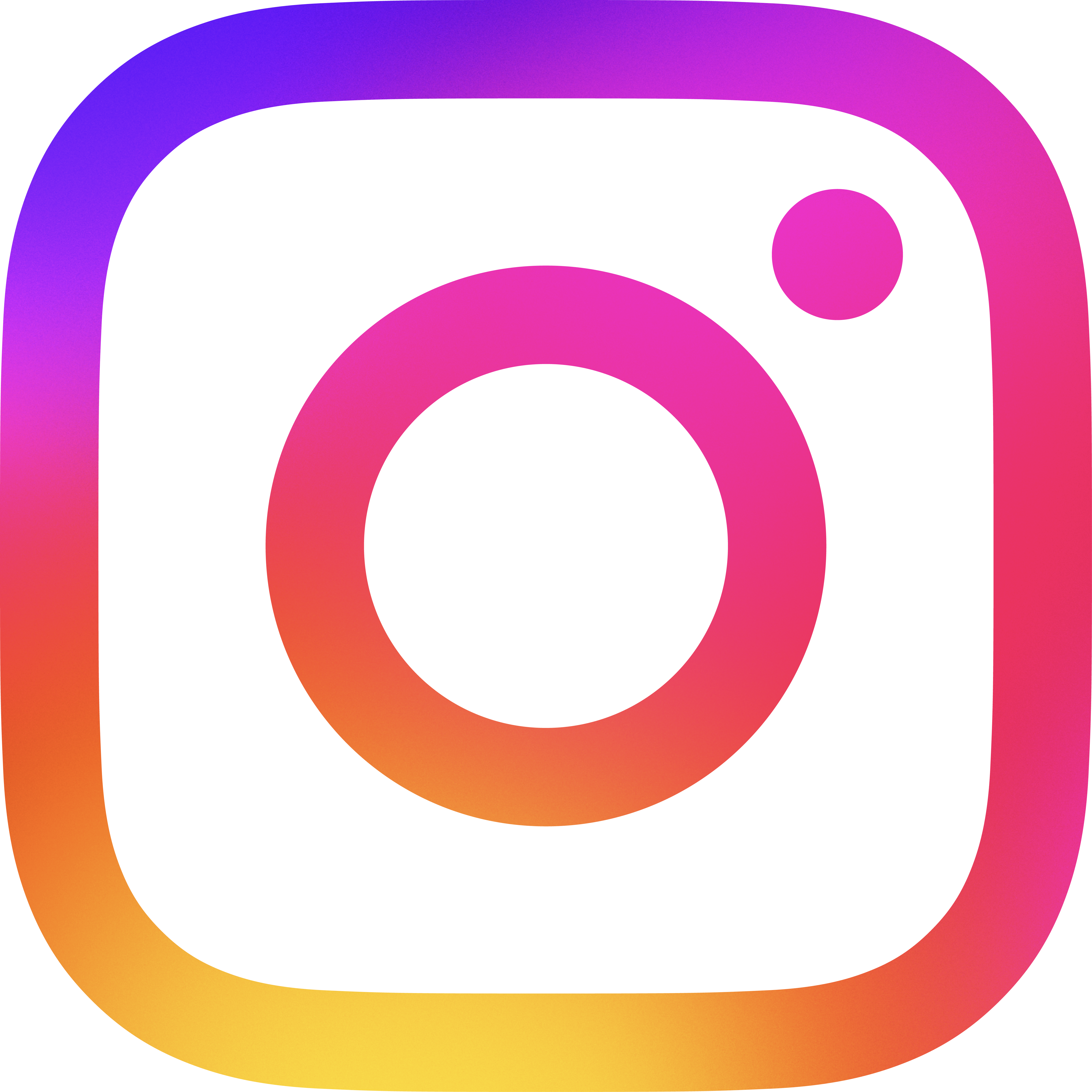平和構築におけるNGOの役割・意義とは?具体的な活動事例とともに解説!

現在、世界のあらゆる地域で武力紛争が発生し、心を痛めている方も多いかと思います。そうした状況では、紛争が終わった後にいかにして平和をつくり、維持するかが重要になっていきます。これが「平和構築」と呼ばれる活動です。本記事では、大きな規模で平和構築を行う国連と対比する形で、現場で人々に寄り添い、きめ細やかな支援を行うNGOの重要な役割について解説していきます。ぜひ最後までお読みください。
平和構築
平和構築とは
そもそも平和構築とは何なのでしょうか。
まず前提として、平和構築には統一された定義はなく、それぞれの機関や団体によって多様な用いられ方をしています。
その中でも、例えば国連は平和構築の目的を以下のように説明しています。
「平和構築は、あらゆるレベルにおける紛争管理のための国家能力を強化することで、紛争の発生または再発のリスクを低減し、持続可能な平和と発展の基盤を築くことを目的とする」¹
その中でも、一般的に平和構築とは、紛争が終わった後に行われる、紛争の再発予防や復興など、その地域にて持続可能な平和が構築されるための活動のことを指すことが多いです。
その活動の例として、和平合意が結ばれた後、真っ先に取り組まれる元戦闘集団や武器を持っている市民の武装解除があります。通常、この活動は「武装解除・動員解除・社会復帰」(英語では、Disarmament, Demobilisation, Reintegration: DDR)という一貫した流れ作業で実施されることが多いです。
その他の平和構築活動としては、行政の再建と民主的な法制度の整備、平和維持のための人材派遣や難民支援などが挙げられ、その活動は多岐にわたります。
ただ、それぞれの国や地域の状況は異なるため、全てに共通する平和構築のプロセスはなく、その地域の文脈によって活動内容は変わっていきます。
こうした平和構築活動には、当該国以外だけでなく、国連をはじめとする国際機関やNGO、現地の市民団体など、さまざまなアクターが参加しています。
国連の役割

上記のアクターの中でも、平和構築と聞くと国連の役割ではないかと思われる方も多いかと思います。実際、国連も平和構築活動に注力しています。
国連の活動は、紛争が勃発する恐れのある要因を克服できるよう国家の能力を高めること、そして市民間の信頼醸成や生活向上のための活動など多岐に渡ります。具体的には、以下のような支援を行っています。
- 安全保障、司法、公共行政の強化
- 対話と和解の支援
- 公共サービスの提供
- 経済の再活性化支援
また、すでに説明したDDR(武装解除・動員解除・社会復帰)は、和平合意後に当事国当局が主体となって実施されるものですが、当事国がDDRに関する知見を欠いている場合が多くあります。そのため、国連は当事国の要請を受け、支援に入ることが多くあります。
このように、国連は大きな規模で対象国を支援しています。
NGOが平和構築を行う意義

NGOとは
前提として、世界共通のNGO(Non Governmental Organization:非政府組織)の定義はありません。
もともとNGOは、国連の会議の場で、政府でも国際機関でもない立場で参加する民間の組織を指す言葉として生まれました。
様々な定義がありますが、例えば日本外務省においては「開発、貧困、平和、人道、環境等の地球規模の問題に自発的に取り組む非政府・非営利組織」²と整理されています。
NGOが平和構築を行う意義
政府や国連が平和構築を行っている中、NGOの平和構築における役割や平和構築活動をする意義は何なのでしょうか。
きめ細かい丁寧な支援
NGOが平和構築を行う意義としては、草の根からのアプローチだからこそできるきめ細かい丁寧な支援がまず挙げられます。
政府や国際機関の行う大規模な支援と異なり、NGOは現場の実行団体としてより地域に根ざした活動をすることができます。
つまり、地域住民の声に直接耳を傾け、国連などの国際機関と連携しながら、これまで支援が行き届かなかった人々に対して一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援を行うことが可能となります。
取り残されがちな層へのアプローチ
NGOは、政府や国際機関から独立した組織です。その活動資金が「寄付」などの自主財源によって支えられている限り、政府機関からの制約を受けにくく、こうした機関が介入しづらい地域や対象者にも、比較的柔軟にアクセスし支援活動が実現できるという特徴があります。
このように、NGOはその独立性と機動性を活かして、真に取り残された人々や課題に対して直接アプローチすることができるということもできます。
結果として、NGOは政府や国連では十分に対応しきれない問題に取り組み、その間にある支援のギャップを埋める重要な役割を果たすことにも繋がります。
中立的な仲介・対話促進・信頼構築
平和構築において、元戦闘員などの紛争当事者が地域社会へと戻っていくことは不可欠です。そのためには、紛争当事者と被害者、そして地域住民との間に存在する対立や不信感を少しずつ解消していく必要があります。
しかし、当事者同士だけで自然に対話の機会を生み出すことは容易ではないこともしばしばです。そこで重要となるのが、第三者による仲介です。
この点において、NGOは中立的な立場を活かし、対話や和解のための場を設けることができます。こうした活動を通じて、紛争当事者と地域社会との間に信頼関係を築き、当事者が社会に復帰するための土壌を整えることが可能になります。
また、地域で対立する複数の勢力が対話し、その分断を乗り越えていくための場を創ることも、NGOができうる仲介のあり方です。

▲パレスチナ和平の実現に向け、当法人が主催したパレスチナの主要政党・組織および市民社会の若手リーダーによる対話会合
取り残された「声」を拾い上げること
真にその地域の平和を実現しそれを持続可能なものとするためには、さまざまな人々の声を丁寧に拾い上げ、誰一人として取り残さないことが重要です。
しかし、紛争にさらされ厳しい状況に置かれている人々は、自らの考えや要望を声にすることが難しい立場にあることもしばしばです。そうした中で、NGOは現場の対象者や環境と直接向き合い、そこから見えてくる細かな課題やニーズを最前線で的確に捉えることができます。
NGOはそうした現場で得た知見を学術に還元し、実践に基づくケーススタディを積み重ねていくことも重要になります³。こうした研究を通じて、政策提言能力を高めるとともに、「声なき声」を世界中に届けることが可能になります。
NGOの平和構築の活動例
ここまで解説してきた通り、これまで平和構築は一般的に「紛争が終結した後」に行われるものとされてきました。しかし現代では、和平合意の成立が困難な紛争、つまり紛争が終結せず長期化する例が増えており、従来の枠組みのままではそうした社会で平和を築くことが難しくなっています。
そのため、和平合意が結ばれていない状況下で、どのようにして平和を構築していくかが新たな課題となっています。こうした現実を受けて、近年では従来の枠を超えた新たなアプローチが生まれ始めています。
そして、私たちの活動もその一つです。アクセプト・インターナショナルは、和平合意を結ぶことが難しい紛争地において、平和構築活動に取り組んでいます。
以下では、先ほど解説したNGOの役割や強みが、現場で実際にどのように活かされているのか、その具体的な取り組みを紹介します。
紛争の当事者に対しての取り組み
まず、紛争当事者に対しての取り組みとして、様々な事情から武装組織に加入してしまった子どもや若者が組織を離脱し、社会復帰できるまでの支援を一気通貫で行っています。
熾烈な紛争地であるソマリアやイエメンに加えて、テロや紛争の影響を受けるケニア、インドネシア、コロンビアなどにおいて、いわゆるテロ組織や武装勢力から離脱した投降兵、刑務所で服役中の受刑者、戦争捕虜などを対象に、以下のような取り組みを実施しています。
投降促進
現地軍や地域コミュニティなどと連携し、いわゆるテロ組織などの武装勢力にいる若者が組織を抜け出すための情報の拡散、投降の受付に加え、最前線での啓発・啓蒙活動などを行っています。
ケアカウンセリング
当事者の抱えている問題を受け止め、平和的な手段を用いてそれを解決するために彼らが何をすべきか共に考えることで、新たな目標・アイデンティティを打ち立てることをサポートしています。
例えば、家族を失った「憎しみ」によりテロ組織に加入する若者に対しては、その思いを「家族への愛」と捉え直し、残された家族を支えるための具体的な手段を共に探していきます。
こうした一人ひとりのニーズに深く寄り添う「きめ細かい丁寧な支援」は、現場に根差したNGOならではのアプローチです。

▲ケアカウンセリングの様子
職業訓練
紛争地においては、経済的に困窮した若者がテロ組織に加入してしまうケースが少なくありません。
そのため、刑務所に収容されている若者や自発的に組織を抜け出した人々に対する社会復帰支援では、出所後に彼らが自ら収入を得られる手助けをするため、職業訓練を行っています。
また、トレーニングで得たスキルを、実際の生活の中でどのように活用するかについても彼らとともに考えます。
このように、単に技術を提供するだけでなく、一人ひとりの希望や将来の不安に寄り添いながら社会復帰への道のりを支えるアプローチは、まさにNGOならではの「きめ細かい丁寧な支援」の実践です。

▲職業訓練の様子
宗教再教育
紛争地では、武装勢力によって過激な思想を強制的に教え込まれ、洗脳されるケースが少なくありません。
しかしながら、その思想を間違いであるとして真正面から否定することは逆効果であることがわかっています。私たちは従来の「矯正」的なアプローチは用いずに、社会との和解、罪と赦し、平和と非暴力などをテーマに議論することで、少しづつ彼らが自分の頭で考えることを後押しし、多角的な視座や批判的思考力を培うことを目指しています。
本来、上記のような武装勢力に関わっていた若者は、セキュリティ上のリスクが高いとみなされ、公的な支援が最も届きにくい「取り残された層」です。私たちはNGOとしての独立性と機動性を活かすことで、政府や国際機関だけでは介入が難しいこれらの対象者にも直接アプローチし、社会復帰への道を切り拓いています。
地域社会に対しての取り組み
紛争当事者の若者が真に社会に戻っていくには、地域社会が彼らを受け入れることが不可欠です。そこで私たちは以下のような取り組みをしています。
地域社会との和解セッション
地域社会と元戦闘員との相互理解を促進するため、地域社会のリーダーたちと元戦闘員を招待し、和解セッションを開催しています。
これはまさに、NGOが中立的な第三者として間に入ることで実現できる平和構築の活動の一つです。当事者同士だけでは対話のきっかけを作ることが難しい中で、私たちが仲介者として相互理解の場を創出し、和解のための土壌を育んでいます。
セッションでは、いわゆるテロ組織に関わらざるを得なかった背景や刑務所での生活について当事者に話してもらうとともに、地域の一員として社会の人々とともに問題を議論することで、和解のための土壌を創っています。
水・食糧・薬などの緊急支援
紛争やそれに伴う災害など被害を受けた地域コミュニティに対して、ニーズに応じて水や食糧、薬などの緊急支援を行い、適切にケアをしていきます。
また、紛争の当事者だった若者も支援活動に参加することで、地域社会との和解にも繋げています。

▲かつて紛争当事者だった若者が参加する緊急支援の様子
国際社会に向けた取り組み
いわゆるテロ組織などの武装勢力の構成員の多くは18歳~35歳の若者で、彼らが武器を置き平和の担い手として社会に戻っていくことが、平和を構築する上で大変重要となります。
しかし、18歳未満の子ども兵と異なり、国際的に彼らを保護するための枠組みは存在しません。このことが、彼らが憎しみの連鎖から離脱することを困難にしています。
そうした問題意識をもとに、私たちは、彼らが直面する複雑な問題を見つめ直す必要性や、彼らを平和の担い手として捉え直すことの重要性などを国際社会に訴えかけています。
これらは、私たちが最前線の現場で紛争の当事者一人一人と向き合い、その声に直接触れてきたからこそ果たせる役割です。
現場で拾い上げたリアルな課題や声を世界へ発信し、2031年までに彼らの教育や保護を実現する国際規範を制定することで、すべての若者が暴力から解き放たれる道を創ることを目指しています。

▲国際規範の制定に向け、国連でスピーチする代表・永井
パレスチナでの取り組み
上記の取り組みに加えて、2023年10月以降の情勢悪化を受け、紛争解決・平和構築を専門とするNGOとしてパレスチナでの取り組みも開始しました。
詳細については、ぜひパレスチナ特設ページをご覧ください。
新たな和平に向けた対話会合
パレスチナの分断の修復と新たな和平に向けたアプローチの創出に向け、主要政党や組織、市民社会の若手リーダーたちによる対話の場を創り、彼ら彼女らと共に新たな和平プロセスの構築に取り組んでいます。
この取り組みは中立的なNGOの立場を活かしたものですが、同時に日本のNGOという善き第三者だからこそ実現できる活動でもあります。
オスロ合意など過去の欧米主導のパレスチナ和平に向けた対話や交渉では、主に年長の指導者が中心となり、女性・若者の声や重要な紛争当事者は排除されてきました。最終的にオスロ合意は破綻し、パレスチナ内部の分断や不信も深まってしまいました。
そのような背景もあって和平の見通しが立っていない中だからこそ、平和的イメージがあり直接の利害関係がない日本で生まれたNGOが、善き第三者としてできうることがあります。何よりも、アクセプト・インターナショナルがこれまでの活動で培ってきた知見や経験があるからこそ、現地の諸勢力からも信頼を得ることができます。
こうした若者主導の新たな和平プロセスは、現在の停滞した状況を打開する新たな可能性となっています。
ガザ地区における緊急人道支援
上記のような和平に向けた中長期的な取り組みと並行して、国連や他のNGO、若手リーダーたちと調整・連携しつつ、ガザ地区の避難民キャンプにて衛生改善、食料・給水支援など今まさに脅かされる命を守るための緊急人道支援も行っています。

▲ガザ地区で行っている給水支援の様子
あなたにできること

本記事では、平和構築の全体像と、そのプロセスにおけるNGOの役割と意義を解説してきました。
NGOは、その独立性と中立性を強みとして、国連や政府機関といった他のアクターだけではカバーしきれない重要な役割を担っています。
持続可能な平和な社会を紛争地で築くためには、政府機関、国連、NGO、民間企業といった多様なアクターが、それぞれの特性と強みを活かして連携し、役割を果たしていくことが重要です。
最後に、世界には、生活の苦しさや洗脳、誘拐など、望まぬまま紛争に巻き込まれてしまった子どもや若者がたくさんいます。彼らは強制的に武装勢力に加入させられ、その多くが戦闘で命を落としています。さらに、紛争が拡大すると、子どもや女性を含む立場の弱い方々が難民・避難民として住む場所を追われるなど、より多くの人が厳しい環境に置かれることとなります。
当法人は本記事で解説してきたような平和構築におけるNGOの果たすべき役割や意義を強く認識し、独立性を保ったまま、ニーズが高いにも関わらず支援の担い手が少ない領域で問題に真摯に向き合い、活動を拡大させてきました。
こうした紛争地での活動は、毎月1,500円(1日50円)から活動を支援していただける「アクセプト・アンバサダー」をはじめとした皆様のご寄付があるからこそ実現できています。
紛争に巻き込まれた子どもや若者たちが「武器」を置き、彼ら自身が平和な未来を創ることを実現する。まさに根本的な問題解決を目指す前例のない挑戦に共感していただけましたら、どうかアンバサダーとして共に歩んでいただけますと幸いです。
ただ、いきなり寄付はハードルが高いと思われる方もいるかと思います。当法人では、活動説明会やドキュメンタリー上映会などのオンラインイベントを無料で開催しております。当法人の活動や紛争地のリアルについてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。
また、当法人では最新の活動状況をお伝えするニュースレターも無料で毎月配信しています。紛争の最前線の状況について定期的に知りたい方はぜひご登録ください。
アンバサダーとは月1,500円(1日50円)からの継続的なご支援をもとに「テロや紛争のない世界」を、ともに目指す「同志」です。毎月1,500円で1年間支援すると、大工などの職業訓練を、テロ組織にいた若者2名に1ヶ月間提供できます。

アクセプトの活動を直接聞けるイベントに参加しませんか?
活動説明会やドキュメンタリー上映会などのイベントを無料で開催しております。活動についてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。

² 外務省「国際協力とNGO」、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo.html、2025年10月31日閲覧
³ 佐藤安信(2004)「人間の安全保障と平和構築の実践的研究・教育のためのNGOの可能性」『Discussion Paper for Peace-building Studies』No.1