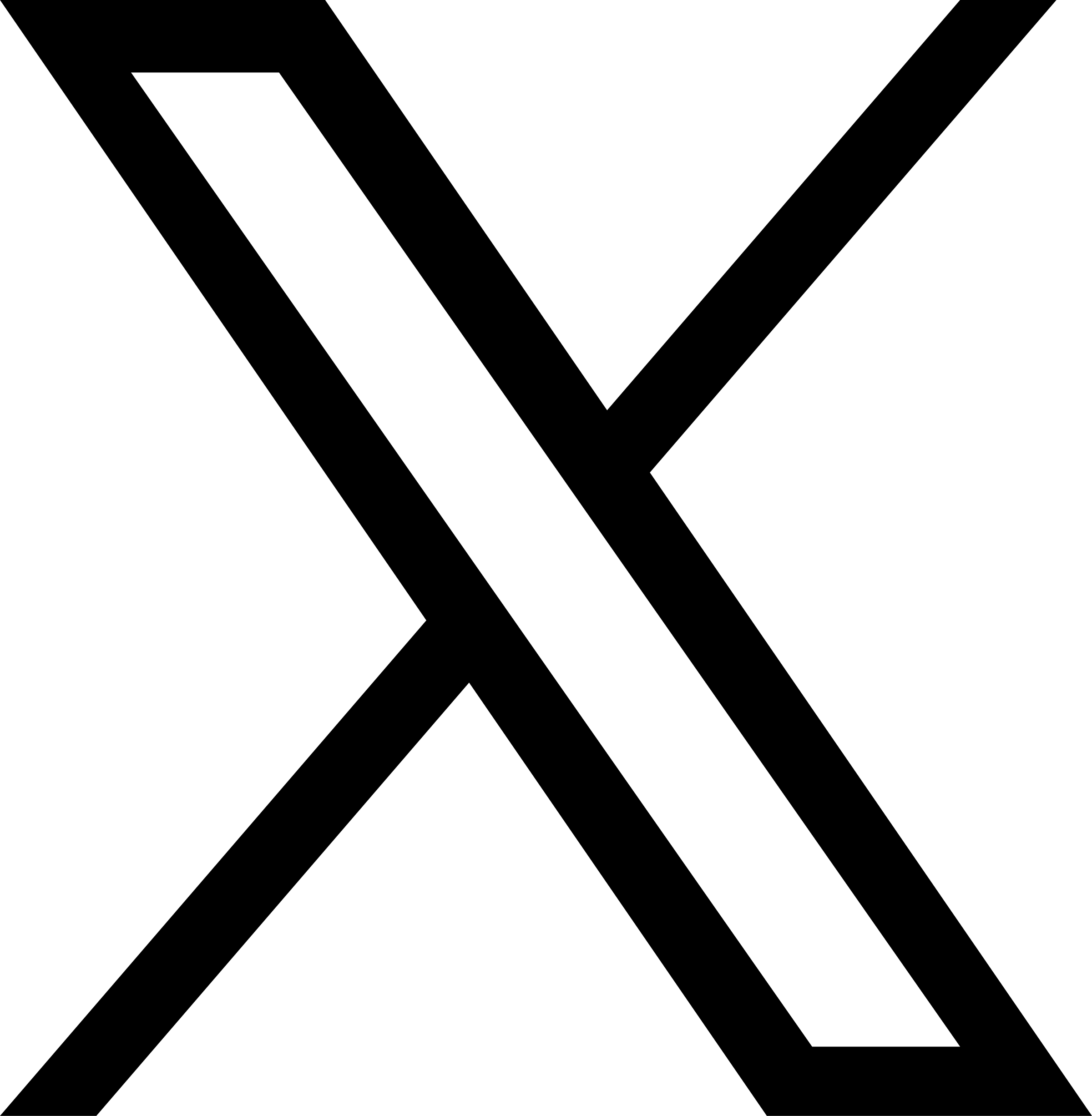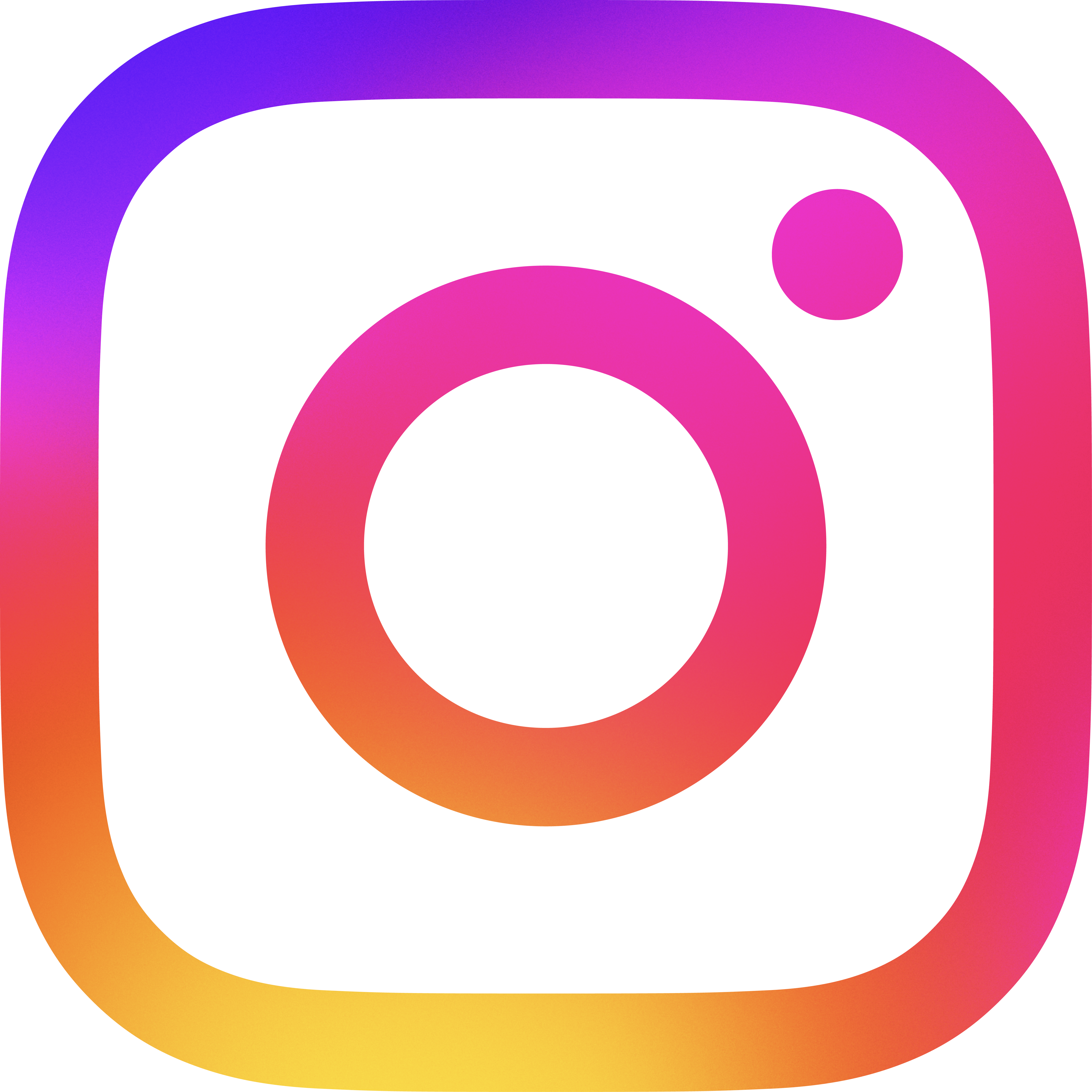寄付の仕方完全ガイドー初心者でも簡単にできる方法と注意点

「寄付をしてみたいけれど、どんな方法があるの?信頼できる団体は?」「少額からでもできるの?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、寄付を始めたい初心者に向けて、具体的な方法から税制優遇までを分かりやすく解説します。
寄付の仕方とは?基本を理解!
寄付とは、個人や企業が社会貢献のために金銭や物品、時間などを提供する行為です。その目的は、貧困支援、教育の充実、環境保護、医療支援など多岐にわたります。
寄付を通じて社会課題解決に貢献できるだけでなく、自身の価値観や信念を形にする手段にもなります。近年は、オンライン寄付の普及やキャッシュレス決済の進化により、手軽に支援できる環境が整ってきました。
しかし、いざ寄付をしようと思うと「どこに寄付をすればいいのか」「寄付金がどのように使われるのか」といった疑問や不安が出てくる方も多くいます。そのため、安心して寄付をするためにも正しい知識を身につけることが大切です。
寄付の種類と方法
寄付にはさまざまな種類と方法があります。自分に合ったやり方を選ぶことで、無理なく社会貢献を続けられます。
寄付できるもの
- 金銭:最も一般的な寄付方法です。
- 物品:衣類、食品、文房具など、団体が求める物資を提供します。
- 資産:不動産や有価証券などを寄付します。
- 時間やスキル:ボランティアやプロボノ(専門的なスキルを活かしたボランティア)として活動に参加する方法です。
具体的な寄付方法
- 定額寄付(例:マンスリーサポート):毎月一定額を継続して寄付する方法です。団体は長期的な活動計画を立てやすくなります。
- 単発寄付:一度の寄付で、自分の好きなタイミングで支援できます。災害支援など緊急性の高い状況で大きな力になります。
- 遺贈寄付:遺言によって財産の一部または全てをNPO法人などに寄付する方法です。詳しくは こちらの記事で解説しています。
- ふるさと納税:自治体への寄付を通じて地域を応援する制度です。自己負担額2,000円で返礼品を受け取ることもできます。
- ポイント寄付:クレジットカードや通販サイトなどで貯めたポイントを、支援団体に寄付できます。
- クラウドファンディング:インターネットを通じて、特定のプロジェクトや活動に資金を提供する仕組みです。寄付型のクラウドファンディングを利用すると、特定の支援活動に対して直接資金を提供することができます。
このように、寄付には多様な方法があるため、自分に合ったやり方を選ぶことが大切です。
寄付のメリット・デメリット
寄付は数ある社会貢献の中でも手軽に始められる方法ですが「本当に役立つの?」「デメリットはないの?」と不安に思う方もいるでしょう。ここでは、寄付のメリットとデメリットを解説します。
寄付のメリット
寄付をすることで、以下のようなメリットがあります。
団体の安定した運営を支えられる
NPO法人などの支援団体は、活動を継続するために安定した資金が必要です。毎月の継続的な寄付は、団体の長期的な支援活動を可能にする大きな力となります。もちろん、一度きりの寄付も重要で、緊急支援などでは大きな助けとなります。
負担が少なく、無理なく支援できる
「一度に大きな金額を寄付するのは難しい」と感じる方も、月1,000円程度の少額から始められる方法もあります。また、日常の買い物で貯まるポイントを1ポイント=1円として寄付できるポイント寄付も注目されており「現金を出すのはハードルが高い」と感じる人でも気軽に社会貢献の第一歩を踏み出せます。なお、継続寄付は一度クレジットカードや引き落とし口座を設定すれば自動的に引き落とされるため、手間なく支援を続けられます。
定期的な活動報告を受け取れる
寄付をすると、多くの団体が定期的な活動報告書やニュースレターを送付してくれます。寄付金がどのように使われたかを知ることで、支援の実感を持ちやすいのが魅力です。
税制優遇が受けられる
日本では、特定の団体への寄付が税制優遇(寄付金控除)の対象になる場合があります。例えば「認定NPO法人」や「公益法人」への寄付が対象となり、確定申告をすることによってその一部が翌年の税金から控除されます。
▶税制優遇に関しましては、こちらの記事で詳しく紹介していますので併せてご一読ください。
寄付のデメリット
寄付を検討する際には、以下の点も理解しておきましょう。
寄付の効果がすぐには見えにくい
寄付によって長期的な取り組みを支援する場合、すぐに目に見える成果が得られないことがあります。災害などが起きて緊急的な支援をする場合は被災者にすぐに届くという特性はありますが、そのような支援ばかりではないため、こうした点には留意が必要です。
寄付の使い道をコントロールできない場合がある
NPO法人等への寄付をした場合、どのプロジェクトにその寄付が割り当てられるかは団体の判断に任せることになります。
もし決まったプロジェクトの支援を行いたい場合は、クラウドファンディングなど寄付金の使い道がはっきりと明示されたものに対して寄付を行うことが効果的です。あるいは、団体によっては寄付の用途を指定することもできるため、事前に確認をしましょう。
一方、多くの団体は支援のプロとして活動を行っているため、基本的にはその時点で最も必要とされていることに寄付を活用しています。そうした信頼のもとに寄付をすることも大切です。
寄付をする前に確認するべきポイント
「寄付先はどうやって選べばいいの?」「せっかく寄付するなら、ちゃんと役立つ団体に届けたい」そう考える方は多いでしょう。
安心して寄付をするために、寄付先を選ぶ際にチェックしておきたいポイントをまとめました。
信頼できる団体を見極める
寄付をする上で最も重要なのは、支援先の団体が信頼できるかどうかを確認することです。悪質な団体や運営が不透明な組織に寄付をすると、本来の目的とは異なる使われ方をする可能性があります。
▶信頼できる団体を見極めるためのポイントは、こちらの記事で詳しく紹介していますので、併せてご一読ください。
寄付先の団体がどのような形の寄付を受け入れているかを確認する
すべての団体が、どんなものでも受け入れているわけではありません。団体によっては、「物よりも現金での寄付」を推奨していることがあります。物品寄付には、郵送コストや仕分けの手間、現地の産業を阻害してしまうリスクなど、いくつかの課題があるためです。
物を寄付したいと考えている方は、不要になった本やCD、洋服などを送って現金化し、それを団体に寄付できる仕組みを利用するのも一つの方法です。例えば当団体ではブックオフによる「キモチと。」やブランディアによる「Brand Pledge」などを活用することが可能です。
詳細については、こちらをご確認ください。
寄付金の使われ方をチェックする
寄付金がどのように使われているかを確認することも大切です。用途が明確でない団体に寄付をすると、意図しない使われ方をされる可能性もあります。具体的には以下のポイントを参考にすると良いでしょう。
経費の内訳が公表されているか
活動費、管理費などの割合が公開されているか確認しましょう。活動内容や成果、支援対象の詳細、年次報告書や収支報告書を公開している団体は、適切な資金管理がなされている可能性が高いと言えるでしょう。
外部機関の監査を受けているか
団体によっては定期的に外部監査を受け、財務報告を適切に公開しています。こうした団体は適切な資金管理がなされている可能性が高いと言えるでしょう。
寄付後に報告書やニュースレターが届くか
しっかりとした団体は、定期的に活動報告を送っています。これにより寄付がどのように活用されたかを確認できます。
人件費に寄付金が使われるのは悪いこと?
「寄付金が人件費に使われるのはもったいない」「中抜きではないか」という声を聞くことがありますが、これは本質を見誤った批判です。
このような意見が出る背景には「人件費=不要なコスト」とし、清貧を美徳とする文化的価値観があります。しかし、現実にはNPO法人などが行う活動の多くは人の力によって支えられており、人件費は必要不可欠な経費です。
大切なのは、人件費が多くを占める事業体とそうでない事業体があることを理解することです。例えば、教育支援を行う団体では、教育を担うスタッフの人件費が多くの割合を占めます。一方で、災害時に緊急支援を行う事業体では、被災者に直接届ける物資の費用が多くを占め、人件費の割合はそこまで大きくありません。そのため、人件費の高さだけでNPOや非営利セクターの善悪を判断するのは本質的ではありません。
さらに、助成金や補助金の中には、人件費としての使用が認められていない、あるいは制限が厳しいものもあります。このため、団体は日常業務を担うスタッフの人件費を自力で確保しなければならないのが現状です。この構造が続く限り、非営利セクターは持続性と人材確保の壁に直面し続けます。寄付は、こうしたギャップを補う柔軟性の高い資金源として、極めて重要な役割を担っているのです。
実際、日本のNPO職員の給与水準は低く、常勤有給職員の人件費中央値は年収200万円から240万円にとどまります¹。この水準では、若い世代がNPOに関わるモチベーションを維持しにくく、非営利業界そのものが縮小する可能性があります。事実、日本のNPO法人の団体数は、ピーク時の2017年から減少傾向にあります²。
一方で、アメリカでは非営利団体への理解や制度設計が進んでおり、NPOで働くことが一般的なキャリアパスとして認識されています。ハーバード大学ケネディスクールの卒業生の約2割が非営利組織に就職しているというデータもあり、非営利セクターが社会の重要な担い手とみなされています³。また、アメリカでは約130万もの団体が寄付金控除の対象となっており、個人寄付の規模も日本を大きく上回ります⁴。
寄付のしやすい制度を整えること、そして、寄付したお金が人件費などに使われることに理解を示すことは、日本の非営利セクターの発展のためにも大変重要です。
寄付の流れと手順

寄付をする際はいくつかのステップを踏むことで、スムーズかつ安心して支援することができます。ここでは、寄付の具体的な流れとそれぞれの方法について解説します。
寄付の主な流れ
- 信頼できる団体を選ぶ:団体の活動内容や実績、財務情報などを確認し、寄付先を決めます。
- 寄付方法を決める: 金銭寄付、物品寄付、ボランティアなど、目的に応じた方法を選びます。
- 寄付の手続きを行う: 選んだ方法に従って、必要な情報を入力し、支払いを完了させます。
- 寄付完了後の確認: 寄付後は、確認メールや領収書を受け取り、保管しましょう。税制優遇を受ける場合に必要になります。なお、領収書の発行時期は団体によって異なります。
- 活動報告の確認: 寄付先団体からの活動報告を確認し、自分の寄付がどのように活用されたかを把握することも大切です。
オンライン寄付のやり方
オンライン寄付はインターネットを通じて手軽に行えるため、多くの団体が導入しています。クレジットカードや電子マネーなど、さまざまな支払方法に対応しているのが特徴です。
- 寄付先の団体の公式サイトにアクセスする
- 寄付金額と支払い方法を選ぶ
- 必要な情報を入力する:名前やメールアドレス、支払い情報を登録します。匿名寄付も可能ですが、その場合、活動報告書や領収書は受け取れません。
- 確認して寄付を完了する
銀行振込・郵便振替での寄付方法
銀行振込や郵便振替を利用した寄付は、特定の団体の口座に直接振り込む方法です。手数料がかかる場合がありますが、振込記録が残るため、証拠として保管しやすいメリットがあります。
銀行振込の場合:公式サイトで口座情報を確認し、ATMやネットバンキングから振込手続きを行います。振込明細書などを保存しておきましょう。
郵便振替の場合:お近くの郵便局の窓口で「払込取扱票」に記入し、振替手続きを行います。
物品寄付の流れと注意点
物品寄付は、衣類や食品などを提供する方法です。金銭寄付と異なり、実際に役立つ物資を直接支援できる点がメリットです。
- 寄付可能な物品を確認する:団体ごとに受け入れ可能な品目が異なるため、事前に公式サイトで確認が必要です。
- 発送方法を選ぶ:直接持ち込む、郵送する、宅配便の寄付プログラムを利用するなど、都合の良い方法を選びます。
- 注意点:使い古したものや破損しているものは送らないようにしましょう。また、団体の倉庫スペースには限りがあるため、事前に相談してから送るようにしましょう。
日本の寄付市場の現状と海外との比較
日本における寄付の実態
2022年の日本人の寄付経験率は44.1%⁵であり、約2人に1人が何らかの形で寄付を行っています。しかし、アメリカやイギリスなど諸外国に比べるとGDPに占める寄付の割合は多くありません。
- 2020年の個人寄付総額:約6,170億円⁶
海外との比較:日本は寄付文化が根付きにくい?
2022年の「世界人助け指数」で日本は118位と低い順位にあります⁷。一方、アメリカでは個人寄付総額が日本の約28倍(約34.5兆円)⁸にのぼります。この差には、税制優遇、寄付先の多様性、遺贈寄付の優遇制度などが影響していると考えられます。
日本でも寄付を増やすための工夫
日本でも寄付を促進するために、いくつかの取り組みが進められています。
- ふるさと納税の普及:地方自治体への寄付で税額控除が受けられる制度です。2022年の寄付総額は約9,653億円と、個人寄付総額を超える規模に成長しています⁹。しかし、都市部の税収減少や返礼品が制度利用の主目的となってしまうという課題も残ります。
- クラウドファンディングの活用:特定のプロジェクト支援が可能になり、2021年度の支援総額は1,642億円と拡大しています¹⁰。
- クラウドファンディングの活用:クレジットカードやQRコード決済で気軽に寄付できる環境が整備されています。Yahoo!ネット募金ではVポイントやPaypayによる寄付も可能で、少額支援がしやすくなっています。
まとめ
寄付には金銭的な支援だけでなく、物品寄付や時間・スキルの提供など、さまざまな形があります。世界では、災害支援、人道危機、教育支援、環境保護など、さまざまな課題に取り組む団体が活動しており、寄付はそれらの活動を支える重要な財源です。
この記事を参考に、ご自身に合った寄付の方法を見つけ、社会のためにできることを始めてみませんか?
最後に、私たちアクセプト・インターナショナルは、世界にはびこる「憎しみの連鎖」をほどくことでテロや紛争の解決を目指しています。
世界には、生活の苦しさや洗脳、誘拐など、望まぬまま紛争に巻き込まれてしまった子どもや若者がたくさんいます。彼らは強制的に武装勢力に加入させられ、その多くが戦闘で命を落としています。さらに、紛争が拡大すると、子どもや女性を含む立場の弱い方々が難民・避難民として住む場所を追われるなど、より多くの人が厳しい環境に置かれることとなります。
こうした現状を変えるために、テロや紛争を終わらせ、平和な世界を実現するための独自の活動をしています。こうした紛争地での活動は、毎月1,500円(1日50円)から活動を支援していただける「アクセプト・アンバサダー」をはじめとした皆様のご寄付があるからこそ実現できています。
紛争に巻き込まれた子どもや若者たちが「武器」を置き、彼ら自身が平和な未来を創ることを実現する。まさに根本的な問題解決を目指す前例のない挑戦に共感していただけましたら、どうかアンバサダーとして共に歩んでいただけますと幸いです。
そして、当法人へのご寄付は、公益財団法人パブリックリソース財団が運営する寄付サイト「Give One」を通じて行うと、所得控除や税額控除の対象となります。なお、手数料の都合上、Give Oneを通じてアクセプト・アンバサダーにご就任いただく場合には、毎月のご寄付金額は2,000円(1日66円)からのご登録をお願いしております。税制優遇を受けながらアンバサダーへのご就任をご希望される際は、ぜひこの制度をご活用ください。詳細はこちらからご覧いただけます。
なお、当法人への直接のご寄付についても寄付金控除の対象にしていただけるよう、現在、厳しい条件をクリアして認定を受けるべく鋭意努力しておりますので、何卒ご理解をいただけますと幸いです。
また、スタッフから活動について直接説明を受けることができる活動説明会やドキュメンタリー上映会などのイベントを、毎月複数回、無料で開催しています。活動についてより詳しく知りたい方はもちろん、スタッフや団体の様子を感じてみたい方は、ぜひお気軽にご参加ください。
アンバサダーとは月1,500円(1日50円)からの継続的なご支援をもとに「テロや紛争のない世界」を、ともに目指す「同志」です。毎月1,500円で1年間支援すると、大工などの職業訓練を、テロ組織にいた若者2名に1ヶ月間提供できます。

アクセプトの活動を直接聞けるイベントに参加しませんか?
活動説明会やドキュメンタリー上映会などのイベントを無料で開催しております。活動についてより詳しく知りたい方は、ぜひご参加ください。

² 内閣府NPOホームページ「特定非営利活動法人の認定数の推移」https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni(2025年8月5日閲覧)
³ Harvard Kennedy School. (2024). “Class of 2024 Employment Snapshot”.https://www.hks.harvard.edu/more/employers/about-our-graduates/employment-snapshot/class-2024-employment-snapshot
⁴ ニッセイ基礎研究所 (2015)「アメリカにおける寄付の現状や特徴」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=42298?site=nli(2025年8月5日閲覧)
⁵ 日本ファンドレイジング協会「調査研究(寄付白書)」https://jfra.jp/research/(2025年8月5日閲覧)
⁶ Ibid.
⁷ CAF「世界人助け指数」、2022、https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf(2025年8月5日閲覧)
⁸ 日本ファンドレイジング協会「調査研究(寄付白書)」https://jfra.jp/research/(2025年8月5日閲覧)
⁹ 村上芽「ふるさと納税額16%増、3年連続最高 宮崎・都城市首位」『日本経済新聞』2023年8月1日 https://www.nikkei.cfom/article/DGXZQOUA315VT0R30C23A7000000/#:~:text=%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AF1%E6%97%A5,%E3%81%A7%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82(2025年8月5日閲覧)
¹⁰ 矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場の調査を実施(2022年)」https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3042(2025年8月5日閲覧)